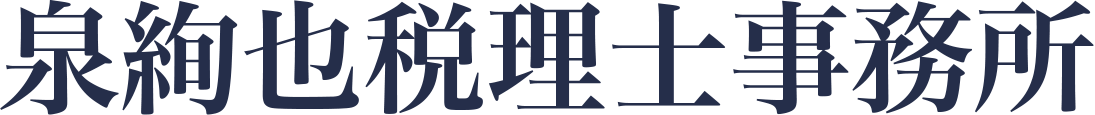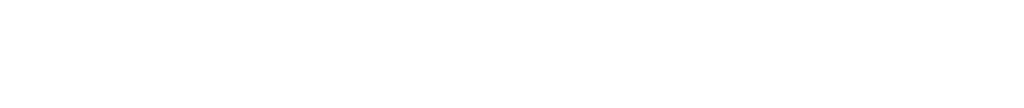国税庁のホームページで公開されている上村和紀「DeFi(分散型金融)の税務上の取扱いについての一考察」税務大学校論叢113 号の紹介です。
引用している資料、検討手法や結論に色々と気になる点はありますが、気になった箇所のご紹介だけいたします。
ただし、「国税庁のホームページに掲載されている=国税庁の公式見解=この論文に書かれていないように従っていれば税務署もその処理を認める」と安易に考えて、ここに書かれている内容を鵜呑みにして、税務処理をすることは避けましょう。
ホームページにも次のような記載があります。
税大論叢掲載論文の内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解を示すものではありません。
もちろん、税務職員が税務調査の際にこの論文を読んで、同じ職員が書いたものということで論文の内容や論拠を特に精査せずに採用して主張してくることも考えられます。このような場面では、各職員の個人的見解に基づいた基本的に行き当たりばったりの主張が多いのが現状です。
ただし、訴訟担当(国税訟務官室)の職員や裁判所においては、この論文の記載内容を鵜呑みにすることはなく、精査した上で、国税庁として支持できる部分は支持する、あるいは裁判所として支持できる部分は支持することになると考えます。
以下、アンダーラインは筆者によるものです。
P48
2 法人税法上の問題点
法人がDEX等において行った暗号資産の預け入れが、暗号資産の「貸付」又は「寄託」に当たる場合には、暗号資産の譲渡が行われるわけではないので譲渡損益は生じず、当該法人が暗号資産を事業年度終了の時に自己の計算において有する場合には期末時価評価の対象となる。
他方で、その預け入れが、暗号資産とDEX等が発行したトークンとの「交換」に当たる場合には、暗号資産の譲渡が行われることとなるため、譲渡損益が益金の額又は損金の額に算入され、「交換」により取得したトークンについては法人税法の暗号資産に該当しない限り期末時価評価の対象とならないこととなる。
すなわち、期末時価評価の対象とならない場合には、法人税法22 条2項、3項の原則どおり、実現した利益のみが所得であるという考え方(実現原則)を採用し、未実現の利得を課税の対象から除外し、未実現の損失、すなわち所有資産の価値の減少は原則として損金には含まれないとの考え方から取得価額が表示されることになろう。
P51-53
3 「貸付」「寄託」「交換」の意義と判断(ユニスワップ及びコンパウンド)
(1)「貸付」の意義と判断について
「貸付」の意義については、①金品や権利を貸与すること。②期限や利子、料金などを定めて金品を貸すこと、③返してもらう約束で、あるものを他人に交付し、または、その物の使用や収益を許容することである(56)。
ところで、自らのトークンペアを提供した引き換えに「LPトークン」や「cToken」を得るのであれば、期限や利子などを定めることなく、いつでも返すことができる性格のものであり、あらかじめ手数料等が定められていたとしても、スマートコントラクト機能によって流動性プールから自律的に支払いを受けるものであって、流動性供給者は多人数に及ぶため貸付として相手方(利用者)から直接的に利子を得たとみることは困難であろう。
したがって、本件代表的な取引を貸付と判断することはできない。
(2)「寄託」の意義と判断について
「寄託」の意義について、寄託契約とは、当事者の一方が物の保管を相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約である(民法657 条)(57)。例えば、Aが所有する物品の保管を委託し、Bがこれを承諾する契約が寄託契約に当たるとされている。
なお、受寄者は原則として、預かった寄託物と同一のものを返還する必要があるが、例外的に「混合寄託」(民法665 条の2)と「消費寄託」(民法666 条)が認められている(58)。寄託契約該当性について検討すると、例えば「混合寄託」では、暗号資産を預けた後も暗号資産の物権的権利が利用者(流動性供給者)に帰属する、いわば混合寄託類似の契約と解する余地があるが、利用者から預かった暗号資産そのものかどうかが区別されないのが通常と思われ、また、利用者もそのような区別を求めていないと思われる、このような通常のケースを想定すると混合寄託類似の契約と解する余地は乏しい(59)。
また、裁判例においては、民法657 条によると寄託契約の対象は物であるが、暗号資産は所有権の客体とはならないから、寄託物の所有権を前提とする寄託契約の成立も認められないと判示したものがある(東京地判平
成27 年8月5日)(60)。このことも考え合わせると、寄託契約とは解しがたいと考えられ消費寄託の該当性も否定されることとなる(61)。
ところで本件取引は、自らのトークンペアを提供した引き換えに「LPトークン」や「cToken」を得たにすぎず、期限や利子などを定めることなくいつでも返すことができる性格のものであり、あらかじめ手数料
等が定められていたとしても、スマートコントラクトを用いて運営され、流動性プールから自律的に支払いを受けるものであって、また、流動性提供者は保管を依頼しておらず、寄託契約として相手方と契約が成立したとみることは困難ではないか。
したがって、本件代表的な取引を寄託と判断することはできない。
(3)「交換」の意義と判断について
「交換」の意義について、交換は当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約束する契約である(民法586 条1項)。
本件代表的な取引においては、「LPトークン」が活発な市場において取引が行われている事実が認められるのであれば、提供した暗号資産の返還を待たずに活発な市場において交換することが可能になるため、財産権を移転しあうことを約束したとみるべきであろう。また、上記(2)のことから暗号資産が所有権の客体とはならないことは明らかであり、財産権の移転を約束する契約という交換の意義に合致するものと考えられる(62)。
また、「cToken」と呼ばれる債権トークンについても、暗号資産取引所において不特定多数の者に対し、他の暗号資産との交換が可能であることから、活発な市場において交換することが可能になるため、財産権を移転しあうことを約したとみるべきであろう。
P61
「LP トークン」が法人税法上、暗号資産に該当し、暗号資産同士が交換され、かつ、活発な市場を有する暗号資産の要件を全て充足するのであれば、法人税法上の期末時価評価の対象になると判断されるものと
考えられる。
P69-70
同法〔筆者注:資金決済法〕2条5項1号において、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」こと及び「不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる」こと(以下「不特定性」という。)がこの要件に関連しており、ブロックチェーン上と暗号資産の定義の関係については、ブロックチェーンは暗号資産の定義の要件ではないが、この要件のうち、パブリック型のブロックチェーン上のトークンは基本的に不特定性の要件を充足し得るという関係にあることからすれば、本件「LPトークン」については暗号資産たる要件を充足しているとみるのが相当である。
本件「LPトークン」は流動性プールを利用して暗号資産を交換したユーザーが支払う手数料の分配を受ける権利証でもあり、DEX(分散型取引所)にステーキング活動をすることで報酬を得ることが可能で、中には、DEX(分散型取引所)に上場され、売買が可能なものもある。このような「LPトークン」は単なる預かり証ではなく、暗号資産である可能性が高いものと考えられる。したがって、暗号資産と認めるのが相当であると考えられることから、預けた暗号資産と「LPトークン(暗号資産)」が交換されたと考え
られ、「交換」により取得し、期末に保有するトークンについては法人税法の暗号資産に該当すると考えられる。
P70-71
cTokenはイーサリアムというパブリック型のブロックチェーン上で管理されるERC20 トークン(ERC20 とは、イーサリアムブロックチェーンで発行されるトークン規格に沿って発行された互換性のある共通規格である。)の標準のトークンであることから、日本法上も暗号資産に該当する可能性が高いものと考えられる。したがって、「LPトークン」や「cToken」は日本法上、暗号資産である可能性が高いものと考えられ、LPトークンと同様に交換されたと考えられ、「交換」により取得し、期末に保有するトークンについては法人税法上の暗号資産に該当すると考えられる。
P73
4 本件LPトークン等の課税上の取扱いについての考察
「LPトークン」という暗号資産であると判定される場合には、税務上、暗号資産同士の交換を行った場合には、所得金額の計算を行うこととされているから、「流動性供給は課税イベントである」という上記3の立場をとることになろう。
また、 レンディングプラットフォームの一つであるコンパウンドで暗号資産を貸し付けた際に発行される「cToken」に代表される債権トークンについても、実務上、「LPトークン」と同様の考え方で処理すべきこととなる。
これらの判定には、英国歳入関税庁(HMRC)における「処分」すなわち(売買、交換、支払、他人への譲渡)という広い概念に関しても、大きな判断材料となるものと考えている。
P74
結びにかえて
日本においてDeFiのサービスについて、会計上の取扱いは会計基準等において明らかされていない。DeFiのサービスは、相当多く存在し、サービスの性質も多岐に渡る。このため対象を明らかにすることなく「DeFiに関する会計上の取扱い」について網羅的に説明するのは困難であると言わざるを得ない。
DEX(分散型取引所)上のDeFi取引利用者は、保有する暗号資産と引換えに「LPトークン」を取得するが、取得した「LPトークン」を暗号資産とみるべきかについては、現状の性質として、市場性があり第三者への売却が可能であること等を勘案すると「暗号資産」であると考えられる。本件において「LPトークン」の取得については、取引の性質が「貸付」や「寄託」とは考えにくく、「交換」に該当すると考えられるが、契約の成立がいつの時点であるのか等、従来の暗号資産等の交換取引とは異なるため、その会計処理については慎重な検討が必要となろう。
暗号資産を預けた者が、その預けた暗号資産に対する支配を完全に手放したわけではないとする議論もあり、「LPトークン」と預けた暗号資産は紐づいていて、「LPトークン」を返却することにより、預けた暗号資産の返却が可能であることから、流動性供給時に暗号資産を流動性プールに入れただけの段階では交換したとみるべきではないとの考え方も首肯できる。また、スマートコントラクトについては、契約の成立と実行が自動化され、いつの時点で契約したかということが捉えにくく更には、それ自体契約といえるのかということについても議論があるなど、今後、日本におけるDeFiに対する規制は、金融規制を所管する金融庁における議論の後、立法化、あるいは既存の規制をもって解釈適用を図っていくことが見込まれることから更なる研究が必要であろ