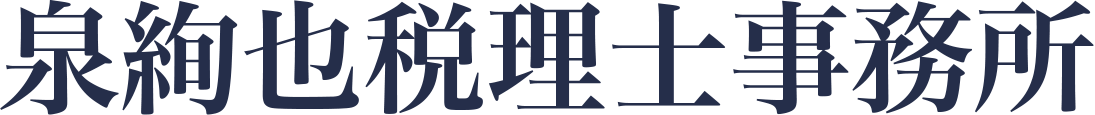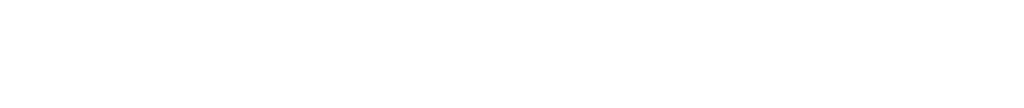国税庁等の審理・訴訟部門に所属する職員が使用している「課税訴訟の手引〔9訂版〕」です。基本的な内容から応用論点までを、訴訟で役立つ内容も盛り込みながら、解説されています。
以下は、目次です。
目次
【第1編】基礎編
第1章租税法の基礎理論とその概要…………………………1
第1 租税法の基本原則…………………………1
1 租税法における租税の意義(1)
2 租税法律主義(1)
(1) 意義と機能(1)
(2) 租税法律主義の内容(2)
ア課税要件法定主義(2) イ課税要件明確主義(3)
ウ合法性の原則(4) エ遡及立法の禁止(4)
オ手続的保障原則と納税者の権利保護(5)
3 租税公平主義(5)
第2 課税要件…………………………7
1 意義(7)
2 概要(7)
(1) 納税義務者(7) (2) 課税物件(7) (3) 課税物件の帰属(7)
(4) 課税標準(7) (5) 税率(8)
第3 各租税の意義及び税額計算の仕組み…………………………8
1 所得税(8)
(1) 意義及び概要(8)
(2) 税額計算の仕組み(8)
ア各種所得金額の計算(13) イ課税標準の計算(13)
ウ課税所得金額の計算(15)
エ税額の計算から申告納税額の算出まで(15)
2 法人税(16)
(1) 意義( 16) (2) 税額計算の仕組み(16)
3 相続税(17)
(1) 意義及び概要(17)
(2) 税額計算の仕組み(18)
ア課税価格の計算(18) イ課税遺産額の計算(18)
ウ相続税総額の計算(19) エ各人の納付税額の計算(19)
4 贈与税(21)
(1)意義及び概要(21) (2) 税額計算の仕組み(22)
5 消費税(23)
(1)意義及び概要(23) (2) 課税の対象(24) (3) 納税義務者(24)
(4) 消費税額の計算の仕組み(24)
ア課税標準の計算(24) イ税額の計算(25)
(5) 国外事業者が行う国境を越えた役務の提供(特定課税仕入れ)に対す
る消費税の課税の仕組みの概略(28)
第2章課税手続の概要…………………………29
第1 納税義務の成立等…………………………29
1 納税義務の成立と確定(29) 2 納期限(30)
第2 納税義務の確定手続…………………………31
1 納税義務の確定の方式(31)
2 国税債権確定の方式(32)
(1)申告納税方式(32) (2) 賦課課税方式(33)
3 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続(33)
(1)概要(33)
(2) 納税申告(35)
ア期限内申告(36) イ期限後申告(36) ウ修正申告(36)
(3) 更正、決定等(36)
ア更正(37) イ決定(37) ウ再更正(37)
エ更正・決定の所轄庁(37) オ更正・決定の期間制限(37)
(4) 更正の請求(42)
ア更正の請求の意義(42) イ通常の更正の請求(44)
ウ後発的理由による更正の請求(48)
4 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続(58)
(1) 税務署長による賦課決定(通則法32条1項1号ないし3号)(58)
(2) 税関長による賦課決定(関税8条).(58)
5 質問検査権(税務調査)(58)
(1)質問検査権の意義(58)
(2) 質問検査権の内容(60)
ア質問検査権行使の相手方(60) イ調査の必要性の要件(60)
ウ質問検査権行使の方法、限度(61)
(3) 質問検査の手続(61)
ア調査手続(調査の事前通知)(61) イ調査の終了の際の手続(63)
(4) 更正、決定等と調査の関係(64)
第3章行政不服申立ての概要…………………………67
第1 不服申立制度の概要…………………………67
1 はじめに(67) 2 再調査の請求の概要(68)
3 審査請求の概要(68)
第2 不服申立てをめぐる諸問題…………………………·69
1 不服申立ての対象となる「処分」の意義(69)
2 不服申立人等(70)
3 不服申立期間と期間徒過の「正当な理由」(70)
(1) 申立期間(70) (2) 期間経過と「正当な理由」(71)
4 審理の併合又は分離(73)
5 審査手続における審査の範囲ー総額主義と争点主義(74)
6 再調査決定・裁決(76)
(1) 理由附記(76)
ア理由附記の趣旨(76) イ理由附記の程度(78)
(2) 裁決の効力(79)
7 書類閲覧請求権の対象と閲覧拒否の「正当な理由」(80)
(1) 書類閲覧請求権の趣旨(80)
(2) 閲覧請求の対象となる物件の範囲(81)
(3) 閲覧拒否の「正当な理由」(81)
(4) 閲覧請求に対する拒否行為の行政処分性(83)
(5) 違法な拒否行為の裁決に及ぼす影響(83)
8 不服申立てと国税の徴収(84)
(1) 不服申立てと処分の効力等(執行不停止、換価の制限) (84)
(2) 徴収の猶予又は滞納処分の続行の停止等(84)
第4章課税訴訟の概要…………………………87
第1 主な課税訴訟の類型…………………………87
1 課税訴訟の種類(87)
(1) 租税訴訟の種類(87)
(2) 行政事件訴訟としての課税訴訟の類型(87)
2 抗告訴訟としての課税訴訟(88)
(1) 処分の取消しの訴え(88)
ア処分性(88) イ取消訴訟の排他的管轄(88)
ウ課税訴訟における処分性(89)
(2) 裁決の取消しの訴え(93)
ア裁決の取消しの訴えの内容(93)
イ取消訴訟における原処分主義(93)
(3) 無効等確認の訴え(94)
ア無効等確認の訴えの内容(94) イ無効事由(98)
(3)
(4) 不作為の違法確認の訴え(101)
(5) 義務付けの訴え(102)
ア非申請型の義務付けの訴え(102) イ申請型の義務付けの訴え(104)
(6) 差止めの訴え(105)
(7) 無名抗告訴訟(106)
(8) 仮の救済制度(108)
ア執行停止(108)
イ仮の義務付け及び仮の差止め(110)
3 当事者訴訟としての課税訴訟(111)
(1) 課税訴訟における当事者訴訟(111)
(2) 予防的租税債務不存在確認訴訟(112)
(3) 源泉徴収による所得税に関する不存在確認訴訟等(113)
4 その他の訴訟(114)
第2 課税処分取消訴訟等における留意点…………………… 114
1 訴えの提起(114)
(1) 課税処分取消訴訟(114)
ア審理の対象・総額主義と争点主義(114)
(ア)問題の所在(115) (イ)総額主義と争点主義(115)
イ課税処分の適法要件(118)
(ア)実体上の適法要件( 118) (イ)手続上の適法要件(118)
(2) その他の訴訟(118)
ア通知処分取消訴訟(118) イ青色申告承認取消処分の取消訴訟(119)
ウ裁決取消訴訟(120) エ無効等確認訴訟(120)
(3) 課税処分取消訴訟等における訴状の記載(120)
ア請求の趣旨と訴訟物(120)
イ請求の趣旨の具体例(120)
(ア)更正処分(120) (イ)賦課決定処分(121)
(ウ)更正の請求に理由がないとする通知処分(121)
(エ)青色申告承認取消処分(121) (オ)審査裁決(121)
(力)無効等確認の訴え(121)
ウ請求の原因(121)
(4) 貼用印紙(122)
(5) 管轄(123)
(6) 税理士補佐人(124)
2 訴訟要件(125)
(1) 広義の訴えの利益(125)
ア訴えの対象(125)
(ア)更正・決定と増額再更正との関係(126)
(イ)更正・決定と減額再更正との関係(133)
(ウ)申告と増額更正との関係(136) (エ)更正と修正申告との関係(140)
(オ)更正をすべき理由がない旨の通知処分と増額更正(145)
イ原告適格(153)
ウ狭義の訴えの利益(154)
(2) 被告適格(157)
ア被告とすべき者等(157) イ被告を誤った場合の救済(158)
(3) 不服申立前置(159)
ア意義(159) イ前置を要しない場合(通則法115条1項ただし書)( 160)
(4) 出訴期間(164)
ア主観的出訴期間(164) イ客観的出訴期間(165)
ウ審査請求があった場合の出訴期間(165) エ出訴期間徒過の救済(165)
3 主張・立証責任等(166)
(1)課税処分取消訴訟における主張・立証責任等(166)
ア主要事実の捉え方(166) イ主張・立証責任の分配(169)
ウ請求原因(177) エ被告の答弁及び抗弁(177)
オ原告の認否及び反論(179)
(2) その他の訴訟類型における主張・立証責任等(180)
ア通知処分取消訴訟(180) イ青色申告承認取消処分の取消訴訟(181)
ウ裁決取消訴訟(181) 二無効等確認訴訟(181)
(3) 裁判上の自白(182)
ア自白の成否(182) イ自白の対象(182) ウ自白の撤回(183)
(4) 信義則・禁反言の法理等(184)
ア租税実体法における信義則・禁反言の法理(184)
イ課税処分取消訴訟における信義則・禁反言の法理(185)
ウ権利濫用の法理(187)
4 文書提出命令(188)
(1)はじめに(188)
(2) 文書提出義務(188)
ア引用文書( 1号)( 188) イ権利文書(2号)( 191)
ウ利益文書(3号前段)( 191) 工法律関係文書(3号後段)( 192)
オ1号ないし3号に基づく文書提出義務と守秘義務(193)
カ4号文書(195)
(3) 文書提出命令の手続(200)
ア申立て(200) イ監督官庁の意見聴取手続(203)
ウ非公開審理手続(204) ニ一部文書提出命令の可否(204)
オ文書提出命令の申立てに対する裁判(206) 力文書不提出の効果(206)
5 判決(207)
(1)判決の種類(207)
(2) 違法判断の基準時(207)
ア行政処分取消訴訟一般についての議論(207)
(5)
イ課税処分取消訴訟の場合(208)
(3) 判決の効力(210)
ア課税処分取消訴訟(210) イ通知処分取消訴訟(214)
ウ青色申告承認取消処分の取消訴訟(214) エ裁決取消訴訟(215)
オ無効確認訴訟(215) 力義務付けの訴え(215) キ差止めの訴え(215)
第3 不服申立てをめぐる訴訟における諸問題……………… 216
1 不服申立てについての判断遅延を理由とする訴訟(216)
(1) 不服申立てについての判断遅延に対する救済方法(216)
(2) 不服申立てについての判断期間(216)
2 再調査決定取消訴訟(218)
(1) 総説(218) (2) 訴えの利益(218) (3) 出訴期間(220)
3 裁決取消訴訟(221)
(1)総説(221) (2) 訴えの利益等(222)
(3) 一部取消・一部棄却裁決(224)
(4) 行訴法10条2項違反の効果(224)
【第2編】応用編…………………………227
第1章租税法の解釈…………………………227
第1 総説…………………………227
1 解釈指針(227)
2 文理解釈(228)
(1) 意義(228) (2) 文理解釈に関する裁判例(228)
3 拡張解釈と限定解釈(233)
(1) 意義(233) (2) 限定解釈に関する裁判例(234)
4 類推解釈(238)
第2 租税法と私法…………………………240
1 租税法と私法の関係(240)
2 固有概念と借用概念(240)
(1) 固有概念(240)
(2) 借用概念(241)
ア学説の状況(241) イ検討(241)
3 私法上の法律行為と租税法(242)
(1) 私法上の法律行為の瑕疵がある場合の取扱い(242)
(2) 錯誤無効の主張(243)
第3 租税回避行為の否認…………………………247
1 租税回避行為の意義(247)
2 租税回避行為の否認(248)
3 事実認定・私法上の法律構成による否認(250)
(1) 意義(250) (2) 契約が不存在、無効などと認められる場合(250)
(3) 契約が不存在、無効などと認められない場合(256)
4 課税減免規定の濫用についての否認(260)
5 タックス・シェルターを利用した租税回避事案(262)
(1) タックス・シェルター(課税逃れ商品) (262)
(2) 裁判例(263)
ア民法上の組合や商法上の匿名組合を利用した租税回避事案(263)
(ア)映画フィルムリース事件(263) (イ)航空機リース事件(264)
(り)船舶リース事件(266)
イ外国の事業体を利用した租税回避事案(267)
ウ外国信託を用いた租税回避事案(270)
第2章課税要件…………………………273
第1 所得税…………………………273
1 総説(273)
(1) 納税義務者(273)
ア個人の納税義務(273) イ法人の納税義務(274)
(2) 所得の意義(275)
ア包括的所得概念(275) イ未実現の所得と帰属所得(276)
ウ違法な所得(277)
エ債務免除益(278) オ非課税所得(280)
2 所得の帰属者の判定(課税物件の帰属の判定)(283)
(1) 判定の基準(283) (2) 裁判例(285)
3 所得の種類・区分(287)
(1) 総説(287)
(2) 各種所得の意義と範囲(289)
ア利子所得(289) イ配当所得(291) ウ不動産所得(292)
工事業所得(296) オ給与所得(299) 力退職所得(304)
キ山林所得(308) ク譲渡所得(308) ケ一時所得(321)
コ雑所得(324)
4 収入金額の意義と帰属時期(権利確定主義)(325)
(1) 総説(325)
ア所得税法の規定(325) イ原則(権利確定主義)(326)
(7)
ウ例外(管理支配基準)(327)
(2) 各種所得の帰属時期(328)
ア不動産所得(328) イ事業所得(329) ウ譲渡所得(330)
エ給与所得(331) オ一時所得(332) 力雑所得(332)
5 必要経費の範囲等(334)
(1) 総論(334) (2) 必要経費の意義及び範囲(335)
(3) 違法支出(339) (4) 家事費又は家事関連費(341)
(5) 親族が事業から受け取る対価(342) (6) 資産損失(346)
第2 法人税…………………………348
1 納税義務者(348)
(1) はじめに(348)
(2) 人格のない社団等の該当要件(350)
(3) 法人税法における課税所得の範囲及び税率(351)
ア①公共法人(352) イ②公益法人等及び④人格のない社団等(352)
ウ③協同組合等及び⑤普通法人(357)
2 法人所得・税額の計算の概要(357)
(1) 法人所得の計算(357)
ア概要(357)
イ税務調整の概要(359)
(ア)決算調整事項(減算項目)(359) (イ)任意的調整事項(減算項目)(361)
(り)必須的調整事項(必須の申告調整事項)(362)
(2) 税額の計算(363)
3 益金及び損金の原則的意義と年度帰属(363)
(1) はじめに(363)
(2) 資本等取引(364)
(3) 益金の原則的意義(364)
ア法人税法22条2項の基本的な規定内容(364)
(ア)概要(364) (イ) 「取引」の意義(366) (り) 「収益」の評価(368)
イ無償取引(368)
ウ低額譲渡(370)
(4) 損金の原則的意義(372)
ア法人税法22条3項の基本的な規定内容(372)
(ア)概要(372) (イ)不正・違法な支出の損金算入の可否(374)
イ債務確定主義(377)
(5) 企業会計及び会社法会計と租税会計(会計の三重構造)(381)
ア会社法会計と企業会計の関係(381)
イ租税会計と企業会計及び会社法会計の関係(382)
ウ公正処理基準の内容(385)
(6) 益金及び損金の帰属事業年度(394)
アはじめに(394) イ益金の帰属年度(権利確定主義)(395)
ウ損金の年度帰属(費用収益対応の原則)(403)
エ損失と収益の両建と年度帰属(412)
4 益金及び損金に関する「別段の定め」(417)
(1)はじめに(417)
(2) 益金に関する「別段の定め」の規定(418)
ア収益の額であるが、益金に算入されないもの(418)
イ収益の額ではないが、益金の額に算入されるもの(421)
(3) 損金に関する「別段の定め」の規定(421)
ア棚卸資産の売上原価の計算(421)
イ減価償却資産の償却費の計算(423) ウ繰延資産(427)
エその他主要な規定の概要(428) オ役員給与等の損金不算入(429)
力寄附金の損金算入制限(434) キ交際費等の損金不算入(440)
5 同族会社等の行為計算の否認(445)
(1) 総説(445) (2) 適用要件(447) (3) 適用例(450)
(4) 非同族会社への適用の可否(452)
(5) 「その法人の行為又は計算」について(453)
6 企業再編・企業結合(454)
(1)グループ法人税制(454)
ア連結納税制度(令和2年度税制改正前)(454)
(ア)総説(454) (イ)納税義務者(455) (ウ)課税物件・課税標準(457)
(エ)税額の計算(459) (オ)申告・納付等(459)
(力)連結納税に係る行為・計算の否認(459)
イ完全支配関係法人税制(グループ法人単体課税)(460)
(ア)総説(460)
(イ)完全支配関係法人間取引に係る課税の繰延措置(460)
(2) 組織再編税制(461)
ア総説(461)
イ法人の合併(462)
.ウ法人の分割(465)
(ア)総説(465) (イ)会社法上の分割(467)
(り)スピン・オフ(特定事業部門分離独立分割)(468) (エ)現物出資(469)
工株式交換及び株式移転(純粋持株会社の設立)(470)
オ法人の解散(清算所得課税の廃止)(472)
力組織再編成に係る行為・計算の否認(472)
(ア)法人税法132条の2の意義、趣旨(472)
(イ)法人税法132条の2の適用要件(474)
(り)法人税法132条の2の「その法人の行為又は計算」の意義(475)
(9)
(エ)裁判例(476)
第3 国際取引と所得課税…………………………477
1 総説(477)
2 非居住者及び外国法人に対する所得課税(478)
(1) 課税原則の変更(478)
(2) 非居住者及び外国法人に対する課税所得及び課税方法(479)
ア非居住者に対する課税所得及び課税方法(479)
イ外国法人に対する課税所得及び課税方法(485)
(3) 国内源泉所得の意義(490)
3 国際的二重課税の排除(495)
(1) 外国税額控除制度の意義(495) (2) 外国税額控除制度の概要(495)
4 国際的租税回避行為の防止(498)
(1) 移転価格税制(498)
ア総説(498) イ独立企業間価格の算定(501) ウ相互協議(505)
エ独立企業間価格の事前確認制度について(506)
オ基本三法による独立企業間価格の算定における諸問題(506)
力基本三法に準ずる方法と同等の方法(511)
キ独立企業間価格を算定するために必要な書類の同時文書化義務(512)
ク独立企業間価格算定に必要な資料の提出等がない場合(514)
ケ比較対象取引の選定が困難な場合(518) コ独立企業間価格の幅(524)
サ独立企業間価格の算定単位(525)
(2) 外国関係会社等合算税制(外国子会社合算税制)(526)
ア総説(526) イ適用要件(措置法40条の4第1項及び第2項) (530)
ゥ'適用除外基準(経済活動基準)( 533)
工適用除外基準に関する近時の改正(541)
オ部分合算課税制度(資産性所得合算課税制度)(541)
(3) 関連者等に対する利子等に関する税制(542)
ア過少資本税制(542) イ過大支払利子税制(545)
第4 相続税・贈与税…………………………546
1 総説(546)
2 相続税の概要(547)
(1)納税義務者(547)
(2) 相続財産の範囲(課税物件)(549)
ア本来の相続財産(549) イみなし相続財産(551)
ウ相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産(554)
エ非課税財産(555)
(3) 税額の計算方法(556)
ア概要(556) イ課税価格の計算(556)
ウ課税遺産額及び相続税総額の計算(558) エ各人の納付税額(559)
3 贈与税の概要(560)
(1) 納税義務者(560)
(2) 贈与財産の範囲(課税物件)(562)
ア本来の贈与財産(562) イみなし贈与財産(563)
(3) 贈与税額の計算の仕組み(564)
ア贈与税の課税価格の計算(564) イ贈与税の税額の計算(564)
ウ相続時精算課税の適用を受ける場合(565)
4 財産の評価基準(566)
(1)概要(566) (2) 不動産の評価(573) (3) 株式の評価(577)
(4) その他の財産の評価(582) (5) 債務の評価(582)
第5 消費税…………………………586
1 総説(586)
2 課税物件(587)
(1) 概要(587)
ア課税の対象となる国内取引(588) イ課税の対象となる輸入取引(591)
(2) 非課税(591)
ア国内取引における非課税取引(消税6条1項、別表第一) (592)
イ輸入取引における非課税取引(消税6条2項、別表第二) (592)
(3) 免税(593)
3 納税義務者(594)
(1)総説(594) (2) 免税事業者制度(免税点制度) (594)
4 課税標準(597)
(1)国内取引(597) (2) 輸入取引(598)
5 税額の計算(599)
(1)総説(599) (2) 仕入税額控除(599)
第 6 附帯税 …………………………610
1 概要(610)
2 延滞税(611)
(1)概要(611) (2) 延滞税の成立と確定(611)
(3) 延滞税の課税要件(612) (4) 延滞税の額(6)’3)
(5) 延滞税の免除(615) (6) 延滞税の消滅時効(616)
3 利子税(616)
(1) 概要(616) (2) 利子税の成立と確定(617)
(3) 利子税の課税要件(617) (4) 利子税の額(617)
(5) 利子税の免除(618) (6) 利子税の消滅時効(618)
(7) 利子税の損金性(618)
4 加算税一般(619)
(1)総説(619) (2) 加算税の法的性質(619)
(3) 本税に関する処分と加算税に関する処分との関係(620)
5 過少申告加算税(622)
(1) 概要(623)
(2) 過少申告加算税の成立と確定(623)
(3) 過少申告加算税の課税要件(623)
(4) 過少申告加算税の額(624)
(5) 過少申告加算税の免除(625)
ア正当な理由がある場合(625)
イ更正を予知してされたものでない修正申告の場合(630)
(6) 過少申告加算税と他の加算税の関係(636)
ア過少申告加算税と無申告加算税との関係(636)
イ過少申告加算税と重加算税との関係(637)
6 無申告加算税(638)
7 不納付加算税(640)
8 重加算税(641)
(1) 意義(641)
(2) 要件(643)
ア行為者(643) イ隠蔽・仮装の意義(651)
(3) 通則法70条5項と同法68条1項との関係(657)
第3章租税確定手続等をめぐる諸問題…………………661
第1 青色申告をめぐる諸問題…………………………661
1 青色申告制度の概要(661)
2 青色申告に係る更正の理由附記をめぐる諸問題(662)
(1) 理由附記の趣旨(662) (2) 理由附記の程度(664)
(3) 理由附記の瑕疵の治癒(668)
(4) 理由附記の不備の補正と更正権の濫用(668)
(5) 更正の理由附記と理由の差し替え(669)
3 青色申告承認の取消しをめぐる諸間題(674)
(1) はじめに(674)
(2) 青色申告承認の取消事由(674)
ア青色申告承認の取消事由の概要(674)
イ帳簿等の提示拒否と帳簿書類の備付け等(675)
ウ「隠蔽」、「仮装」の意義(678)
工取消事由該当性と税務署長の裁量(678)
(3) 青色申告承認取消しにおける理由附記(679)
ア理由附記の趣旨.程度(679)
イ理由差し替えの制限(680)
(4) 青色申告承認取消処分の取消しと更正処分との関係(680)
(5) 青色申告承認取消しの期間制限の有無(682)
第2 推計課税における主張・立証…………………………683
1 総説(683)
(I) 推計課税の意義(683)
(2) 推計課税の本質(684)
ア事実上推定説(684) イ補充的代替手段説(685)
2 推計の必要性(689)
(1) 意義(689)
(2) 推計の必要性の要否(690)
ア学説の状況(690) イ裁判例の状況(691)
ウ推計課税の本質論との関係(693)
(3) 推計の必要性の具体的認定(調査非協力要件) (695)
(4) 青色申告承認取消事由との関係(697)
3 推計の合理性(698)
(1) 問題の所在(698)
(2) 推計方法の種類(699)
ア比率法(699) イ効率法(700) ウ資産増減法(700)
(3) 推計方法選択の合理性(701)
ア事実上推定説からの検討(701) イ補充的代替手段説からの検討(702)
(4) 同業者率による推計(703)
ア同業者率による推計の具体的方法(703)
イ同業者率による推計の合理性をめぐる問題(706)
4 実額反証と逆推計(716)
(I) 実額反証(717)
ア問題の所在(717) イ実額反証の時期(718)
ウ実額反証の主張・立証責任(719) エ実額反証の立証の程度(722)
オ部分的実額反証の可否(723)
(2) 逆推計(729)
第3 源泉徴収所得税をめぐる諸問題…………………………730
1 概説(730)
(1)源泉徴収制度の意義(730) (2) 瀕泉徴収制度の概要(731)
2 源泉徴収制度の合憲性(733)
(13)
3 源泉徴収義務の成立要件(734)
(1) 瀕泉徴収の対象となる所得等(734) (2) 支払の意義(734)
(3) 源泉徴収義務者(支払をする者)(735)
(4) 源泉所得税における推計課税(738)
4 源泉徴収をめぐる法律関係(739)
(1) はじめに(739) (2) 国と支払者との関係(739)
(3) 支払者と受給者との関係(745) (4) 国と受給者との関係(747)
第4章課税をめぐる国家賠償訴訟………………………… 749
第1 はじめ|こ………………………………………………….. •749
1 序(749)
2 国賠法の制定と明治憲法下の「国家無答責の法理」(749)
第2 国賠責任の成立要件…………………………751
1 公権力性(752) 2 職務関連性(754) 3 違法性(755)
4 故意・過失(757) 5 因果関係及び損害(758)
6 課税処分取消訴訟と国賠訴訟の関係(759)
第3 類型別裁判例…………………………759
1 課税処分の国賠訴訟(759)
2 質問調査に関する国賠訴訟(763)
(1) 納税者方への立入行為等(764)
(2) 質問検査権の行使方法(事前通知の有無等)(766)
(3) 税理士・弁護士への応対(768)
3 税務上の行政指導(770)
(1) 税務相談等における誤回答・誤指導の場合(770)
(2) 修正申告の慾憑(しょうよう)・勧奨の場合(773)
(3) 行政指導の不作為(774) :
事項索引………………………… 777
判例索引…………………………783