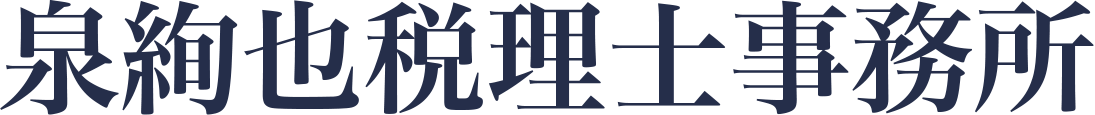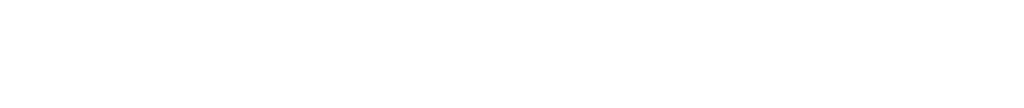以下は、照会者が、個人が行う暗号資産の貸付け(レンディング)に係る所得税の課税関係について照会したものの、東京国税局が、照会者に対し、次のとおり、文書回答の対象とならないことを回答した際の決裁資料からの抜粋です。
個人が暗号資産の貸付けを行った際や返還を受けた際に、その時点で含み損益を課税所得計算に入れなければならないのかが問題となりますので、文書回答の対象にならなかったのは残念です。そもそも、本当に「文書回答の対象に当たらない」といういべきなのか疑わしいのですが(ただし、個人的には、他の国税局と比べて、東京国税局は文書回答に対して積極的に取り組んでくれています。)、国税庁は「文書回答=納税者サービス」という姿勢を堅持していますので、文書回答の対象にならないという決定や、対象となってもその回答に不満がある場合に照会者としては不服申立てを行うルートがないという問題があります。
ただし、本件においては、「本件貸付けの時及び照会者がA社から暗号資産の返還を受けた時において、貸借した暗号資産と同種同量の暗号資産の返還を受ける限りにおいては、貸し付けた及び返還を受けた暗号資産の含み益(損)に係る所得税の課税は生じない」旨の口頭回答がなされています。議論すべき点は残っていますが、暗号資産の貸付けの課税関係に対する国税庁の見解を推測する際に参考になるでしょう。
文書回答の対象となる事前照会は、「取引等に係る税務上の取扱い等が、法令、法令解釈通達あるいは過去に公表された質疑事例等において明らかになっているものに係る事前照会でないこと」及び事前照会の内容が「国税に関する法令以外の法令等に係る解釈等を必要とするもの(当該法令等により決定されるべき事項が未解決であるものを含む。)」ではないことを要件の一つとして実施しておりますが、御照会の取引については、この要件を満たしておりません。
以下は、照会資料からの抜粋です。「???」は情報公開請求で入手した資料の黒塗り部分です。
照会者は、A社と暗号資産に係る消費貸借契約(本契約)を締結して、A社に対し、???を、???から???までの???間、貸付け(本件貸付け)、A社から、本件貸付けに係る賃借料として、貸付け数量???の???に相当する数量の???を受領することとした。
本件貸付けにかかる課税関係については、次のとおり取り扱って差し支えないか。
1. 本件貸付けの時において、貸し付けた???の含み益に係る所得税の課税は生じない
2. 照会者がA社から???の返還を受けた時において、同???の含み益に係る所得税の課税は生じない。
3. 賃借料については、本件貸付けの契約期間終了日における市場価額で換算した価額が所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入金額となり、所得税の課税対象となる(消費税の課税対象となることは承知している。)。
3 検討
(1) 暗号資産に係るこれまでの整理
イ 資金決済に関する法律の規定
資金決済に関する法律第2条《定義》第5項は、暗号資産とは、次のものをいうと規定している。
(イ) 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
(ロ) 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる上記財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるものまた、令和元年6月法律第28号による改正後の資金決済に関する法律'(以下「改正資金決済法」という。)により創設された第63条の19の2《対象暗号資産の弁済》第1項は、暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が同法第63条の11《利用者財産の管理》第2項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有するとし、同条第2項は、同条第1項の規定について民法第333条《先取特権と第三取得者》の規定を準用すると規定している。
ハ 民法の規定等
所有権は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利であるところ(民法206)、その客体である所有「物」は「有体物」をいい(民法85)、「有体物」とは、「無対物」に対する概念で、液体・気体・固体といった空間の一部を占めるものであり、「無対物」とは、権利や自然力(電気・熱・光)のように姿のないものを指すとされている(内田貴『民法I(第4版) 総則・物権総論』、東京大学出版会、353頁)。
暗号資産に係る裁判例をみると、東京地裁平成27年8月5日判決(ビットコイン引渡等請求事件)は、所有権の対象となるには、有体物であることのほかに、所有権が客体である「物」に対する他人の利用を排除することができる権利であることから、排他的に支配可能であること(排他的支配可能性)が要件となると解されており、ビットコインは、所有権の客体となるために必要な有体性及び排他的可能性を有するとは認められないため、ビットコインは物権である所有権の客体とはならない旨判示している。
また、東京高裁令和2年12月10日判決(仮想通貨権利移転手続等請求事件・???上告受理申立て中)は、民法上、物とは有体物のことをいい、有体物とは空間の一部を占めて、有形的な存在をいうと解されているのに対し、ビットコインを含む暗号資産は、電子的方法により記録される財産的価値であるにすぎず、空間の一部を占める有形的なものでないことは明らかであるため、ビットコインを含む暗号資産は有体物とはいえず、ピットコインを含む暗号資産を寄託の目的物とする寄託契約は成立し得ない旨判示している。
なお、改正資金決済法第63条の19の2が準用している民法第333条は、先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができないと規定している。
ニ 租税法におけるこれまでの整理
(イ)消費税法
消費税法上、暗号資産は支払手段に類するものとして、暗号資産の取引については消費税を課さないこととされている(消法6、別表ーニ、消令9④)
また、国税庁令和3年12月「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(以下「現行FAQ」という。)では、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税法上の「資産の貸付け」に該当することから、消費税の課税対象となる旨の取扱いが示されている。
(ロ)所得税法
所得税法上、暗号資産については、その譲渡原価等の計算及び評価の方法並びに取得価額は規定されているが(所法48の2、所令119の6ほか)、その他の事項は規定されていない。
暗号資産の譲渡に係る所得区分を巡る議論では、平成31年3月20日第198回参議院財政金融委員会第5号によると、議員からの質問に対し、暗号資産は資金決済法上「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されており、消費税法上も「支払手段に類するもの」として位置づけられていることから、暗号資産の譲渡益は、資産の値上がりによる増加益とは性質を異とするものと考えているため、暗号資産は「資産」ではあるものの、「譲渡所得の基因となる資産」には該当せず、その所得は、一般的に譲渡所得には該当しないものとして取り扱っている。また、暗号資産については外国通貨と同様に、本邦通貨との相対的な関係の中で換算上のレートが変動することはあっても、それ自体が価値の尺度
とされており、「資産の価値の増加益」を観念することは困難と考えている旨の回答がなされている。
また、暗号資産の一般的な課税関係を巡る議論では、平成26年3月に閣議決定された参議院議員からの質問主意書に対する答弁書によると、(質問の前提とする「ビットコインによる取引」の内容が明らかでないことから一概に回答はできないとした上で)一般論としては、所得税法、法人税法及び消費税法等に定める課税要件を満たす場合には、課税の対象となる旨の回答がなされている。
なお、現行FAQでは、レンディングにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税の課税対象となり、その取得した暗号資産の取得時点の価額について所得の金額の計算上総収入金額に算入される旨明らかにされている。
(2) 所得税法における「収入すべき金額」の意義
所得税法第36条第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とするとしているところ、この文言からすれば、同項は、外部からの経済的価値の流入を「収入」と捉えて、いるものと解するのが相当であるとされている(山口地裁平成31年2月13日判決)。
(3) 検討
民法上、消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずるものとされているところ(民法587)、暗号資産は、上記(1)ハのとおり所有権の客体とならないと解した裁判l例がある一方、未だ係争中の事案もあり、必ずしも暗号資産に係る私法上の取扱いが明らかにされていない。
他方、改正資金決済法は、必ずしも暗号資産に係る私法上の取扱いが明らかにされていないことを踏まえ、個別に、暗号資産に係る暗号資産交換業者とその利用者との間における取引上、利用者が暗号資産の移転を目的とする債権に関し優先的に弁済を受けることができる権利を認めているものと解することができる。
この点、暗号資産に係る取引について私法上どのような関係が成立しているか、本件でいえば暗号資産が民法上の所有権の対象になっていないことをどのように捉えるか(「取得」の範囲)は措くとして、暗号資産に係る課税関係を検討するに当たっては、所得税法第36条の課税要件(趣旨)を踏まえ、契約当事者間の合意した契約内容に基づき何らかの外部からの経済的価値の流入があったと認めることができるか否かにより検討することが相当であると考える。また、このように解することは、平成26年3月の答弁書の内容(上記(1)二(ロ)) とも齟齬しない。これを本件についてみると、契約当事者間である照会者とA社が合意した契約内容は、????、暗号資産の貸借であると認められる。
また、改正資金決済法第63条の19の2にて(暗号資産交換業者との取引ではあるが)暗号資産の移転を目的とする債権に関し他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有するとされていること(上記(1)イ)及びこれまでの租税法上の整理において暗号資産に資産価値の増加を観念することは困難であると示されていること(上記(1)二(ロ)) を併せ考えると、暗号資産の貸主である照会者は、暗号資産をA社に貸し付けるために移転させることで、その貸し付けた暗号資産について優先的に弁済を受ける権利が生じ、その権利に基づき同種同量の暗号資産の弁済を受けるものであって、これら各時点における暗号資産の含み益(損)は評価上のものと解することが相当であり、照会者に何らかの外部からの経済的価値の流入があったと認めることはできない。
他方、???暗号資産を貸借したことにより生じる経済的価値の流入であると認めることができる。
ところで、現行FAQにおいて、「レンディング」により暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税の課税対象となる旨明らかにされているところ、暗号資産のレンディングとは、暗号資産取引所においては、一般に、暗号資産取引所が利用者から暗号資産を借り受け、一定期間預かった上で返却する際、あらかじめ決めておいた利用料を上乗せして支払うというものと説明されており(注)、現行FAQで想定している「レンディング」もこれと同様のものとも考えられる。
しかしながら、暗号資産を借り受けて、一定期間預かった上で返却する際に、あらかじめ決めておいた賃料を上乗せして支払うことは、暗号資産取引所以外の者でも行うことは可能であり、当該者が暗号資産取引所であるか否かにより、課税上の取扱いを異にする特段の理由も見当たらないことからすれば、本件貸付けのように、会社に暗号資産を貸し付けてその賃借料を得るようなものも上記「レンディング」に含めて取り扱っても差し支えない。
以上を踏まえれば、本件貸付けの時及び照会者がA社から暗号資産の返還を受けた時において、貸借した暗号資産と同種同量の暗号資産の返還を受ける限りにおいては、貸し付けた及び返還を受けた暗号資産の含み益(損)に係る所得税の課税は生じない。
また、本件賃借料については、???が所得税法36条1項に規定する収入金額となり、所得税の課税対象となる。
(注)暗号資産厚顔業者の???のホームページにおいては、???と説明されている。
4 結論等
(1)結論
イ 本件貸付けの時及び照会者がA社から暗号資産の返還を受けた時において、貸借した暗号資産の含み益(損)に係る所得税の課税は生じない。
口 本件賃借料は、???が所得税法36条第1項に規定する収入金額となり、所得税の課税対象となる。
(2) 文書回答の可否
本照会に対しては、本照会は、平成14年6月28日付課審1-14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の1に定める文書回答を行う対象となる事前照会の要件(7)取引等に係る税務上の取扱い等が、法令、法令解釈通達あるいは過去に公表された質疑事例等において明らかになっているものに係る事前照会でないこと及び(9)口国税に関する法令以外の法令等に係る解釈等を必要とするもの(当該法令等により決定されるべき事項が未解決であるものを含む。)ではないことを満たしておらず、文書回答の対象となる事前照会には該当しないことから、文書回答を行わず「文書回答の対象となる事前照会に当たらない旨のお知らせ(通知)」を照会者に通知することとしたい。