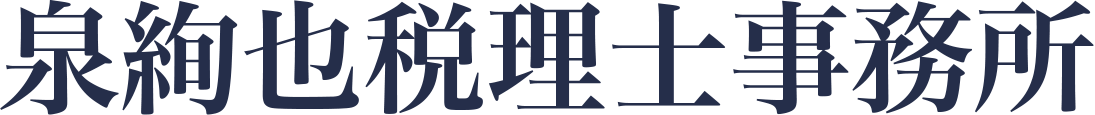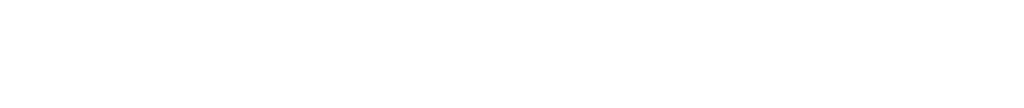親族の健康状態等の事情により調査を受けられる状況にないため調査の延期を申し出たにもかかわらず、税務職員が本件調査を強行したことは、質問検査権の範囲を逸脱・濫用に当たるかが争われた裁決事例(国税不服審判所裁決令和6年6月7日)の紹介です。
「親族の看取り」を理由に税務調査の延期を申し出た納税者に対して、調査を進めた税務職員の対応は違法なのか?――この点が争点となった令和6年6月7日付国税不服審判所裁決(仙裁(諸)令5-10)を紹介しています。
本記事では、長期間無申告だった個人事業者に対して税務職員が反面調査等を実施した経緯や、納税者が「親族の健康状態」を理由に調査の延期を希望した際の対応が、質問検査権の濫用にあたるか否かが詳細に審理された裁決内容を解説しています。
📌 税務職員の調査権限の及ぶ範囲、納税者の私的事情とのバランス、調査の実施時期や反面調査の適法性など、税務調査実務にかかわる方必見の内容です。
裁決要旨
請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)に対し、親族の健康状態等の事情により調査(本件調査)を受けられる状況にないため調査の延期を申し出たにもかかわらず、本件職員が本件調査を強行したことは、国税職員が遵守すべき昭和51年4月1日付国税庁の税務運営方針の定めに従っておらず、本件調査は質問検査権の範囲を逸脱、濫用したものであることから、本件調査に原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。
しかしながら、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第74条の2≪当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権≫第1項に規定する質問検査権の行使については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方との私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解されているところ、請求人は帳簿等を作成せず長期間無申告であったこと、本件職員は請求人に対して事業に関する具体的な質問や書類提示を受けて検査を行うことができなかったこと、本件調査の一環として反面調査を行っていることなどから、本件調査は客観的な必要性があり、その方法や態様も相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまっていたといえ、その実施の時期も含め、権限ある税務職員の合理的な選択によるものと認められる。したがって、本件調査に原処分を取り消すべき違法はない。(令6. 6. 7 仙裁(諸)令5-10)(国税不服審判所裁決要旨より)
裁決文抜粋
(「〇〇」は不開示部分、不開示部分の推測です。一部省略して記載しています。)
1 事実
(1)事案の概要
本件は、原処分庁が、〇〇業を営む審査請求人は消費税等の納税義務があるとして消費税等の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、原処分に係る調査には、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した質問検査権の濫用があったとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
(2)関係法令
(3)基礎事実
イ 請求人について
・〇〇という屋号で〇〇を営む個人事業者
・請求人は、平成16年~令和2年課税期間の消費税等の確定申告書を提出せず
「ロ 平成20年10月の請求人と原処分庁所属の職員との間のやり取りについて
(イ)原処分庁所属の職員は、平成20年10月、請求人が消費税等の申告をしていなかったため申告を促す電話をした。その際、請求人は、仕事上のトラプルや自身の体調不良のため申告できなかった、〇〇にいうおばに申告額の集計を依頼している、請求人から連絡するから待ってほしいなどと応答した。
(ロ)原処分庁所属の職員は、平成20年12月、請求人からの連絡がなかったため、請求人に電話をした。その際、請求人は、集計を頼んだおばの体調不良等があり、平成21年2月下旬から3月にまとめて申告するつもりなのでそれまで待ってほしい、必ず連絡するのでそれまで待ってほしいなどと応答した。
(ハ)請求人は、その後、原処分庁所属の職員へ連絡をせず、消費税等の申告もしなかった。
(ニ)原処分庁は、上記の後、令和3年10月14日の実地の調査を開始するまで、請求人に接触しなかった。」
ハ 請求人の〇〇等について
ニ 請求人の状況について
「ホ 令和3年10月14日以降に行われた調査について
(イ)原処分庁所属の調査担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)は、令和3年10月14日、通則法第74条の9 《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定による通知をすることなく、請求人の事業所に臨場し、請求人に対し、諸求人の消費税等の質問検査等を行う旨等を通知し、実地の調査を開始した(以下、同日以降に行われた原処分に係る調査を「本件調査」という。)。本件調査に際し、請求人は、本件調査担当職員の質問には応答したものの、請求人の〇〇等を理由に、調査の延期を要望した。
これに対し本件調査担当職員は、請求人の【親族】の事情は察するが、前回請求人が必ず連絡するから待ってほしいと申述してから10年以上過ぎており、調査として臨場しているのでこれ以上待つことは考えていないなどと説明した。
なお、請求人は、本件調査担当職員の帳簿の作成状況に関する質問に対して、請求人の母親が事業をしていた頃は帳簿をつけていたと思うが、今は利益も出ていないので帳簿は作成していない旨回答した。
また、請求人は、請求人の事業に係る書類等を留置きして検査する旨の本件調査担当職員からの申出に応じなかった。
(ロ)本件調査担当職員は、令和3年10月15日、同月19日、同月20日及び同年11月1日、請求人の取引金融機関に臨場等し、請求人の預金の状況等を調査した。
(ハ)本件調査担当職員は、令和3年11月2日、請求人に電話をしたが請求人は不在であった。そのため、本件調査担当職員は、電話に応答した者に請求人から折り返し連絡をするよう依頼したが、請求人からの連絡はなかった。
(ニ)本件調査担当職員は、令和3年11月16日、請求人の事業所に臨場した。その際、請求人は、【親族】の看護及び同年12月で終了する取引先との話合い等があり余裕がないため、調査は年明けまで待ってほしい旨申し述べ、調査の延期を要望した。
これに対し本件調査担当職員は、年明けなら対応すると確約できるかなどと応答した。
なお、請求人は、本件調査担当職員に対して、請求人の母親が事業をしていた頃は経理の従業員を雇い帳簿も作成していたが、請求人が事業を引き継いでからは帳等は作成していない旨申し述べた。
また、請求人は、請求人の事業に係る書類等を留置きして検査する旨の本件調査担当職員からの再度の申出に応じなかった。
(ホ)本件調査担当職員は、令和3年11月30日、請求人に電話をしたが、請求人の応答はなかった。
(へ)本件調査担当職員は、令和3年12月2日、請求人に電話をし、請求人に対して、直接会う機会を設けて、請求人の事業に係る帳簿及び書類等の提示をするよう依頼した。これに対し請求人は、請求人の従業員が病気になったことや、〇〇したことを申し述べ、具体的な日程の調整をする前に電話を切った。
(卜)本件調査担当職員は、上記(へ)の後も、令和3年12月16日ないし令和4年4月26日にかけて、請求人に電話をし、又は請求人の事業所や居所に臨場するなどしたが、請求人と連絡をとることはできなかった。
(チ)本件調査担当職員は、令和4年4月12日、請求人の取引金融機関に臨場し、請求人の預金の状況等を調査した。
(リ)本件調査担当職員は、令和4年4月14日ないし同月21日にかけて、請求人の取引先の事業者に臨場し、請求人との取引について調査をした。そして、本件調査担当職員は、請求人が平成27年ないし令和2年において、上記取引先に対して〇〇等を譲渡し、その対価を得ていたことを把握した。
(ヌ)本件調査担当職員は、令和4年5月12日、請求人に電話をし、請求人に対して、請求人の【親族】が亡くなったことに弔意を伝えるとともに、実地の調査に応じてほしい趣旨の要請をした。これに対し請求人は、商工会を介して税理士をお願いしたのでもう少し待ってほしいと応答したが、具体的な日程の調整などは行われなかった。
(ル)本件調査担当職員は、上記(ヌ)の後も、令和4年5月20日ないし令和5年2月8日にかけて、請求人に電話をし、又は請求人の事業所や居所に臨場するなどしたが、請求人と連絡をとることはできなかった。」
2 争点
本件調査に原処分を取り消すべき違法があるか否か。
3 争点についての主張
4 当審判所の判断
「(1)法令解釈
通則法第74条の2第1項の規定は、国税庁、国税局又は税務署の調査権限を有する職員において、当該調査の目的、調査すべき事項、申請、申告の体裁内容、帳簿等の記入保存状況、相手方の事業の形態等諸般の具体的事情に鑑み、客観的な必要性があると判断される場合には、職権調査の一方法として、納税義務者やその取引先など同項各号規定の者に対し質問し、又はその事業に関する帳簿、苦類その他当該調査事項に関連性を有する物件の検査を行う権限を認めた趣旨であって、この場合の質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当である(最高裁昭和48年7月10日第三小法廷決定・刑集27巻7号1205頁参照)。
(2) 検討
請求人は、上記3の「請求人」欄のとおり、税務運営方針及び国税庁訓令に従っていないことを理由に、本件調査は質問検査権の範囲を逸脱、濫用したものである旨主張するところ、税務運営方針は、税務行政の一般的あるいは原則的な方針を示したものであり、また、国税庁訓令は、国税庁の職員が事務を実施するに当たっての基準を示したものにすぎないから、以下では、上記(1)の法令解釈に沿って、本件調査が質問検査権の範囲を逸脱、濫用したものであるか否かを検討する。
請求人は、上記1の(3)のイ及びホのとおり、事業所を設けて営業活動をしていたところ、平成16年以降、消費税等の確定申告を全くしていなかったことに加え、本件調査においては、本件調査担当職員に対して帳簿等は作成していない旨申述していたことからすれば、請求人が、自ら納税義務の有無の判定や課税標準額等の算定を行い、長期にわたる無申告状態を是正することは、極めて困難な状況であったといえるから、原処分庁は、請求人の納税義務の有無を確認し、納税義務がある場合にはそれを履行させるべく、請求人に対して質問検査をし、本件調査の対象であった課税期間及びその基準期間の課税資産の譲渡等の対価の額などを調査する必要があったといえ、本件調査は客観的に必要であったと認められる。
また、本件調査担当職員は、請求人の本件調査の延期の要望には応じずに本件調査を実施しているところ、このことは、上記1の(3)のロの請求人の過去の態様や同ホの(ハ)のほか一連の本件調査における請求人の態様からすれば、請求人の要望のとおりに請求人からの連絡があるまで本件調査の実施を見合わせたとしても、請求人が本件調査担当職員に連絡しないであろうことは合理的に推認され、請求人の要望のとおり本件調査を延期した場合、請求人の無申告の状況を容認する帰結になる蓋然性は高かったといえるから、本件調査担当職員が請求人の要望に応じずに本件調査を行ったことには合理的な理由があり、本件調査の実施の時期は、本件調査時における請求人の事情を考慮しても、権限ある税務職員の合理的な選択であったと認められる。
そして、本件調査の態様をみると、上記1の(3)のホの(イ)、(ニ)、(へ)及び(ヌ)のとおり、本件調査担当職員は、本件調査を通じて、請求人が本件調査担当職員の要請に応じなかったため、請求人に対して事業に関する具体的な質問や、請求人から書類等の提示を受けて検査を行うことができなかった一方で、同(ロ)、(チ)及び(リ)のとおり、本件調査の一環として、令和3年10月15日から令和4年4月21日にかけて、金融機関及び取引先に対していわゆる反面調査を行ったことが認められる。これらの反面調査は、①請求人が、〇〇などを理由に調査の実施に難色を示し、調査の延期を申し出るとともに、帳簿は作成していないと申述して帳簿及び書類等を提示せず、本件調査担当職員の書類等の留置きの要請にも応じなかったために行われたものと認められること、②本件調査担当職員が、請求人に対し継続的に連絡をとろうとしても請求人からの応答がなく、帳簿及び書類等の調査ができなかったために行われたものと認められること、及び、③その態様は、請求人の消費税等の納税義務の有無及び課税標準額等の算定を目的として、その範囲内で行われたものと認められることから、請求人の納税義務の確認及び課税標準額等の算定のために必要なものであったといえる。また、本件調査において、請求人を質問検査のために長時間にわたって拘束したような事実も見受けられない。
したがって、本件調査は、客観的な必要性があり、その方法や態様も相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまっていたといえ、その実施の時期を含め、権限ある税務職員の合理的な選択によるものと認められるから、本件調査に原処分を取り消すべき違法はない。
(3) 請求人の主張について
イ 請求人は、上記3の「請求人」欄のとおり、原処分庁は、請求人の調査の延期の申出を無視して本件調査を強行したのは、請求人の【親族】と残り少ない時間をともに過ごし【親族】の最期を看取るという私的利益を侵害する社会通念上容認される限度を超えるものである旨主張する。
確かに、本件調査が開始された時点において、請求人の〇〇は芳しくなかったかった事実が認められ、請求人が何ら理由なく本件調査の延期を申し出たわけではない。
しかしながら、上記(2)で説示したとおり、本件調査は客観的に必要であったと認められ、その態様をみても、本件調査担当職員は、請求人に対して事業に関する具体的な質問や検査を行っておらず、原処分庁は、本件各決定処分の納付すべき税額を反面調査により算出している。そして、本件調査担当職員が請求人に対して行った質問は、帳簿及び書類等の作成、保存の有無の確認やその提示を求めるといった、通常、当然に行われるものであって、その時間も限られたものであり、本件調査担当職員が、請求人に対して長時間にわたって質問検査をした事実も、請求人が【親族】の看護をすることや【親族】と一緒に過ごし【親族】の最期を看取ることを妨害するのを意図して殊更に調査を行ったような事実も認められないのであるから、本件調査は、請求人の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度を超えるものではない。
なお、請求人は、原処分庁が請求人の無申告状態を放置していたとも主張するが、長期間にわたって全く申告をしなかったのは請求人であり、その間、原処分庁が調査を行うなどの是正措置を講じなかったとしても、そのことは上記結論を左右するものではない。
(4) 本件各決定処分の適法性について
上記(2)のとおり、本件調歪に原処分を取り消すべき違法はなく、当審判所においても、本件各課税期間の消潰税等の納付すべき税額は、本件各決定処分の納付すべき税額と同額であると認められる。
また、本件各決定処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
したがって、本件各決定処分はいずれも適法である。
(5) 本件各賦課決定処分の適法性について
上記(4)のとおり、本件各決定処分はいずれも適法であり、期限内申告苔の提出がなかったことについて、通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし筈に規定する「正当な理由」があるとは認められない。
そして、当審判所において、通則法第66条第1項及び第2項に基づき本件各課税期間の消潰税等に係る無申告加算税の額を計算すると、本件各賦課決定処分における金額といずれも同額であると認められる。
したがって、本件各賦課決定処分はいずれも適法である。
(6) 結論
よって、審査請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり裁決する。