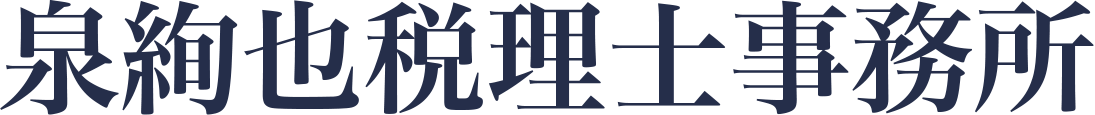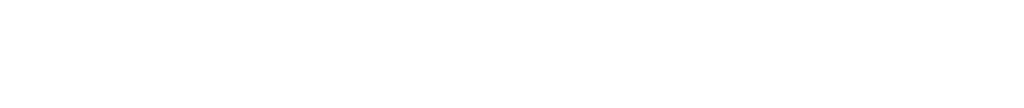以下、東京国税局の課税第一部個人課税課「書面添付制度の意見聴取に関するFAQ」の抜粋です。
書面添付制度は、税務代理する税理士等に限らず、広く税理士等が作成した申告害について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨から設けられたものです。
本制度は、平成21年4月24日付東局課一個5-19「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続き等について」事務運営指針に基づき運用することとなりますが、制度の理解を更に深め、その趣旨を踏まえた適正・円滑な運用を行い、制度の普及・定着を図る必要があります。
本資料では、本制度の運用に当たり留意すべき事項等を問答方式により取りまとめましたので、執務の参考として活用してください。
問1 書面添付制度とは、どのようなものですか。
答 書面添付制度とは、税理士法(以下「法」といいます。)第33条の2第1項又は第2項に規定する書面(以下「添付書面」といいます。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関してその者に調査通知して調査する場合において、当該租税に関して法第30条の規定による書面(以下「税務代理権限証書」といいます。)を提出している税理士又は税理士法人
(以下「税理士等」といいます。)があるときには、事前通知をする前に、当該税理士等に対し、添付書面に記載された事項に関して意見を述べる機会を与えなければならないというものです(法35①)。
また、添付書面が添付されている申告書について更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士等が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときには、申告書及びその添付書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従っていないことが明らかであること又はその計算に誤りがあることにより更正を行うときを除き、当該税理士等に対し、当該事実に関して意見を述べる機会を与えなければならないこととされています(法35②)。
問2 書面添付制度に基づく調査通知前の意見聴取とは、どのような性格のものですか。
答 意見聴取は、税務の専門家としての立場を尊重して付与された税理士等の権利の一つと位置付けられ、添付書面を添付した税理士等が申告に当たって計算等を行った事項に関することや、意見聴取前に生じた疑問点を解明することを目的として行われるものです。
したがって、こうした制度の趣旨・目的を踏まえつつ、意見聴取により疑問点が解明した場合には、結果的に調査に至らないこともあり得ることを認識した上で、意見聴取の機会を積極的に活用し、例えば、顕著な増減事項・増減理由や会計処理方法に変更があった事項・変更の理由などについて個別具体的に質疑を行うなどして疑問点の解明等を行い、その結果を踏まえて調査を行うかどうかを的確に判断します。
問3 申告書の作成に関する計算事項等記載書面の第1面「1 提示を受けた帳簿書類に関する事項」欄から第3面「5 総合所見」欄までに全く記載がないような場合であっても、意見聴取を行うことになりますか。
答 そのような書面は、法第33条の2第1項に規定する記載事項が記載されていないものであり、同項に規定する添付書面に該当しないものですから、そのような書面が添付されていたとしても、補正依頼、意見聴取等を行う必要はありません。
なお、当該添付書面に該当しない事案について実地の調査等を実施する場合には、調査通知を行う際(調査通知を行わない場合には税理士等との接触の際)に添付書面に該当しない旨を説明し、じ後の適切な記載等が図られるよう指導します。
問4 添付書面に記載されている税理士等と税務代理権限証書に記載されている税理士等とが異なる場合には、いずれの税理士等に対して意見聴取を行うことになりますか。
答 税務代理権限証書に記載されている税理士等に対して意見聴取を行うことになります。
問5 現在税務代理権限を有しているとして税務代理権限証書に記載されている税理士等と、申告書の提出時における税務代理権限証書に記載されている税理士等とが異なる場合には、いずれの税理士等に対して意見聴取を行うことになりますか。
答 現在税務代理権限を有しているとして税務代理権限証書に記載されている税理士等に対して意見聴取を行うことになります。
問6 調査対象期間が3年間である場合において、最終年分の申告書には添付書面の添付がなく、前年分又は前々年分の申告書に添付書面が添付されているときには、前年分又は前々年分に関して意見聴取を行うことになりますか。
答 前年分又は前々年分に関して意見聴取を行うことになります。
その際には、前年分又は前々年分に係る税務代理権限証書に記載されている税理士等に対して意見聴取を行うのではなく、現在税務代理権限を有している税理士等に対して意見聴取を行うことになります。
問7 意見聴取は、どのような時期に、どのような方法で行うのですか。
答 統括官等(特別国税調査官、統括国税調査官、情報技術専門官、国際税務専門官、審理専門官又は特別記帳指導官)は、調査通知予定日の1週間から2週間前までに税務代理権限証書に記載されている税理士等に対して意見聴取を行う旨を口頭(電話)で連絡し、意見聴取の日時及び方法を取り決めます。
この場合、意見聴取は、調査通知予定日の前日までに了することとし、原則として税理士等に来署依頼する方法により行います。また、添付書面の「事務処理」欄に意見聴取を行う旨を通知した日及び調査通知予定日を記入します。
(注)1 税理士等が遠隔地に所在している場合など来署が困難な場合には、電話による意見の聴取又は文書による意見の提出によっても差し支えぁりません。
2 意見聴取は、統括官等が行い、原則として調査担当者が同席します。
3 意見聴取に際しては、税理士等に対して帳簿等の持参及び提示を求めないこととします。
問8 意見聴取を行った後、調査着手前に修正申告書が提出された場合、加算税の取扱いはどのようになりますか。
答 意見聴取における質疑等は、調査を行うかどうかを判断する前に行うものであり、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものですから、意見聴取における質疑等にのみ基因して修正申告書が提出されたとしても、当該修正申告書の提出は、更正があるべきことを予知してされたものには当たりません。
したがって、この場合には、加算税を課さないことになります。
問9 反面調査を実施するに当たり、反面調査先の申告書に添付書面が添付されている場合には、当該反面調査先の税理士等に対して意見聴取を行うことになりますか。
答 意見聴取は、法第35条第1項において、「当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合」に行うこととされています。
一方、反面調査は、調査対象者と取引関係にある者に対してその取引内容を確認するために行うものであり、当該反面調査先の申告書に係る租税に関して調査を行うものではありません。
したがって、反面調査先の税理士等に対して意見聴取を行うことにはなりません。