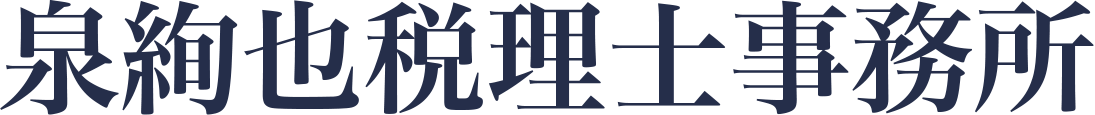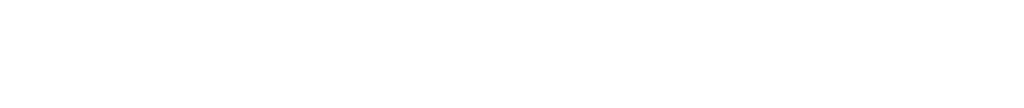不動産取引によって生じた外国為替差益に対して所得税が課された東京地裁令和7年2月5日判決では、暗号資産の取得価額の計算に関する解釈等が示されています。
納税者(原告)が、暗号資産の取得価額の計算に関して個別法を定める所得税法施行令119条の2 第2項を根拠として、不動産取引に係る外貨の取得時の円換算額の算定においても個別法を用いるべきである旨主張しましたが、裁判所は、暗号資産と外貨の類似性を認めつつもの、この主張を受け入れませんでした。
黄色の下線部分や本件の結論について、暗号資産ではなく外貨への個別法の適用を考えた場合に、個人的には別の解釈論もあるかなと考えています。他方で、暗号資産の個別法に関する議論の参考にもなるでしょう。
原告は、暗号資産の取得価額の計算に関する所得税法施行令119条の2 第2項を根拠として、本件各不動産取引に係る部分については、外貨の取得時の円換算額の算定において個別法を用いるべきである旨主張する。
ア 確かに、暗号資産は、外貨と同様に、物理的な劣化による価値の減少が想定されず、同一の種別である限り代替性を有し、取得価額が異なっても、ー単位ごとに認められる権利や性質、価値などは変わらないといえるため、外貨と類似の性質を有するということができる。
もっとも、所得税法施行令11 9条の2が、暗号資産の取得価額の計算につき、取得価額を平均化する方法(総平均法又は移動平均法)を原則としつつも(同条1項)、例外として、「暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得」につき、平均化の対象に含めないものとしたのは(同条2項)、暗号資産の中には、全世界的に通貨(外貨を含む。)との交換ができず、特定の暗号資産とのみ交換できるものがあるところ、このような暗号資産の交換等のために一時的に必要となった暗号資産を含めて取得価額の平均化をすることは実態に合わないためであると解される。したがって、同項の規定が適用されるのは、暗号資産の中でも、全世界的に通貨との交換ができないという限られた暗号資産の交換等の場面に限定されると解される。(以上につき、乙2 3、32参照)
イ これを本件各不動産取引についてみると、まず、本件各不動産は、通貨(ドル)と一般的に交換可能である。
そして、原告は、本件借入れ①の直前である平成29年8月31日において、本件外貨建預金口座に5901万8616.04.ドルを保有していたところ(別表2-1・順号100の⑤欄参照)、この金額は、原告が本件各不動産の取得のために行った本件各送金の総額1437万1436.93 ドルの4 倍を超える金額である(前提事実(2) 、(3)) 。しかも、本件各証 拠によっても、原告が本件各借入れ前に保有していたこれらのドルをもって本件各不動産を購入することができなかったとの客観的な事情は見当たらない。
そうすると、本件各借入金につき、本件各不動産取引のために「一時的に必要」なドルの取得であったということはできない。
ウ原告は、所得税法施行令119条の2第2項の「一時的に必要な」の解釈等に関し、①本件各不動産取引の前から原告が本件各不動産を購入するに足りるドルを保有していたことは「一時的に必要な」取得に該当するか否かの判断に影響を与えない、②???銀行との契約上、本件各借入金を本件各不動産の取得のために用いることが義務付けられていた、③原告が本件各借入れ前から保有していたドルは、外国為替投資事業の結果として保有していたものであり、不動産事業とは区別する必要があり本件各借入れの必要があったなどとして、本件各借入れが同項の「一時的に必要な」ドルの取得である旨主張する。
しかし、暗号資産(A)を購入するために暗号資産(B) を購入する場 合において、当該暗号資産(B)の購入以前から当該暗号資産(A) を購入するに足りる十分な量の暗号資産(B) を有していたときは、当該暗号資産(B) の購入は「一時的に必要なj取得に当たらないと解するのが文理解釈として自然かつ合理的であり、また、為替レートの変動を踏まえた利益操作を防止する観点からも相当である。
さらに、仮に、原告が???銀行との間で、本件各借入金を本件各不動産の取得のために用いる旨の契約上の義務を負っていたとしても、それらの義務は本件各借入れに係る各金銭消費貸借契約を締結したことによって生じたものにすぎず、原告が本件各借入れ前に保有していたドルを本件各不動産の取得のために用いることができなかったことを基礎付ける事情ではない。
しかも、本件各借入金が入金された本件口座は、本件各借入れ及び本件各送金以外の取引にも用いられており(乙1) 、原告が本件各不動産取引と他の取引とで使用する口座を区別していた様子はうかがわれない上、仮に原告が使用する口座につき何らかの区別をしていたとしても、そのような主観的な事情は、本件各借入金が本件各不動産取引のために「一時的に必要」な取得であったことを基礎付ける事情とはいえない。
したがって、原告の上記①から③の主張は、いずれも理由がない。
小括
以上によれば、本件外貨建取引のうち本件各不動産取引に係る部分についても、所得税法施行令11 9条の2第2項に準じて個別法を用いることはできないというべきであり、本件各為替差益の算定における外貨の取得時の円換算額の算定は、総平均法に準ずる方法によるべきである
以下の記事も参考にしてください。
不動産取引によって生じた外国為替差益に対して所得税が課された東京地裁令和7年2月5日判決【暗号資産の個別法の流用は認めず】