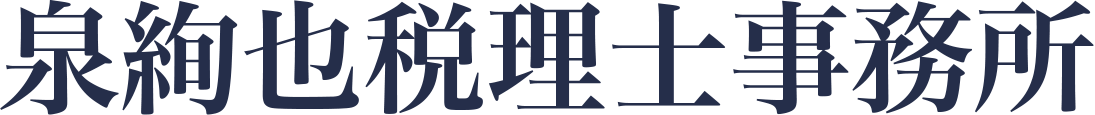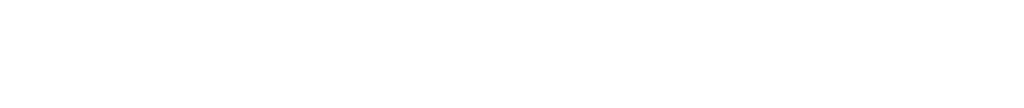令和7年5月13日、大学院在学中にご指導を賜りました 中央大学法科大学院教授・酒井克彦先生 がご逝去されました。突然の訃報に接し、いまだ深い喪失の思いを抱えたままではございますが、多くの方々から温かいお言葉を頂戴する中で、少しずつ前を向かなければとの思いに至り、筆を執らせていただきます。
先生のご逝去が公となった後、多方面より、先生がご担当されていた講義や研修講師のご依頼を多数頂戴いたしました。これらをお引き受けすることは、微力ながらも弟子としての務めであり、先生のご遺志を少しでも受け継ぐ営みであると深く受け止めております。
先生が見つめておられた風景の一端に、僭越ながら自らが立たせていただいているという現実に日々向き合う中で、先生を失ったことの現実が徐々に胸に迫り、深い悲しみは募るばかりでございます。
酒井先生は、租税法学における卓越した識見と膨大な業績を有されるのみならず、後進の育成にも並々ならぬ情熱を注がれ、多くの研究者・実務家から篤い尊敬と敬愛を集めておられました。ご指導の場においては常に厳しく、そして温かく、法の解釈における精緻な論理と誠実な姿勢を私たちに身をもって示してくださいました。そのお言葉の一つひとつが、今なお私の研究と教育の礎として確かに息づいております。
先生と初めてお目にかかりましたのは、平成18年2月17日、税務大学校の専科研修においてでございました。
当時、税大の教育官であった先生は、「租税回避否認論・導入―これから実践に戻る諸君へ」と題する講話において、私法上の法律構成による否認論をはじめ、租税回避の否認に関する多岐にわたる議論を縦横無尽に展開された後、講義の締めくくりに、若き研修生たちに向けて、力強くこうお話になられました―
「みなさん、どうか、条文をよく読み、疑問を持ち、そして仲間とよく議論をしてください」。
租税法律主義が厳然と存在する租税法領域において、条文に真正面から向き合い、真摯に学び、そして仲間と対話を重ねることの大切さを説かれたそのお言葉と、後輩職員たちに向けて熱い思いを込めて語りかけられる先生のお姿は、今も鮮明に記憶に残っております。
その後、租税法の研究を本格的に志すようになった私は、既に当局をご退官され国士舘大学で教鞭を執られていた先生に、直接お電話を差し上げ、ご指導をお願い申し上げました。突然の申し出にもかかわらず、先生は快くお引き受けくださり、平成21年10月11日、初めて酒井ゼミに参加させていただく機会を得ました。
その後、修士課程から博士課程へと進学し、酒井先生の中央大学ご転任に伴い、私も同大学大学院商学研究科へと進学しました。平成29年3月、先生のご指導の下で念願の博士号を取得いたしました。
同年、私は、千葉商科大学にて教員としての第一歩を踏み出し、令和5年4月より東洋大学にて職を得て、現在に至っております。まだまだ未熟な弟子ではございますが、教員採用の報告を差し上げた際、まるでご自身のことのようにお喜びくださった先生のお姿が、今なお私の胸に温かく残っております。
最後に先生にお目にかかることができたのは、令和7年2月14日、税務大学校で開催された税務研究会の席上でした。先生の御前で研究報告をさせていただき、貴重なご指導を賜ることができたこと、また、ご多忙の中にもかかわらず懇親会にもご出席くださり、直接お話しできたことは、私にとって何よりの光栄であり、生涯忘れることのできない思い出となっております。
振り返れば、私は先生と二人で深く語らう機会に恵まれることが多く、とりわけ研究の在り方について、何度もご薫陶を賜りました。条文に対する厳格な文理解釈の姿勢、徹底した先行研究調査の重要性、そしていかなる時も学生の問いに誠実に応える姿勢―これらの一つひとつを、先生は言葉と実践とをもって私に教えてくださいました。その教えとお人柄は、これからも私の学問的営みにおいて、変わることなき道標であり続けると信じております。
今後、先生のご厚恩に直接お応えする機会を永く失ってしまったことは、痛惜の念に堪えません。
しかしながら、これまで賜りましたご指導とご高配に深く感謝申し上げるとともに、
謹んで哀悼の意を表し、酒井克彦先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
令和7年5月22日 泉 絢也