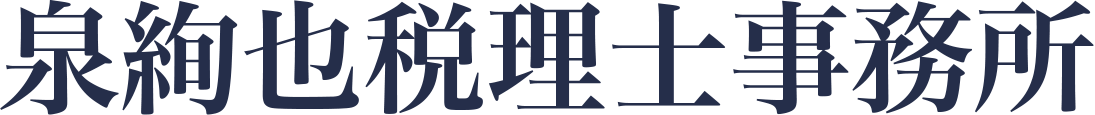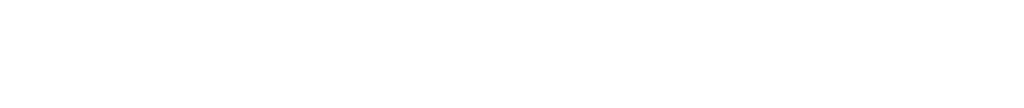デリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)の運営において、名義人と実際の経営者が異なる場合、所得はどちらに帰属するのでしょうか。
本記事では、令和6年1月9日に出された国税不服審判所の裁決を詳しく解説します。本件は、名義を貸した会社員が、実際には経営を支配していなかったとして所得の帰属を争った事案です。審判所は「実質所得者課税の原則」に基づき、所得が名義人ではなく実質的な経営者に帰属することを認め、課税処分を取り消しました。
一方で、一度提出した「修正申告」を錯誤によって取り消せるかという重要な争点では、厳しい判断が示されています。名義貸しのリスクと、税務調査後の対応における注意点を、最新の裁決から学びましょう。
審判所のホームページ掲載の裁決要旨
請求人は、請求人が関わっていた事業(本件事業)に係る所得は請求人に帰属せず、また、請求人が提出した各修正申告書等(本件各修正申告書等)については、税理士の誤った説明を請求人が信じて錯誤に陥ったことにより提出したものであり、本件各修正申告書等により負担する税額も多額であるから、請求人に対する重加算税等の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)は、錯誤を理由として取り消されるべきである旨主張する。確かに、本件事業に係る所得は請求人に帰属しないものの、本件事業から生ずる収益を享受する者が誰であるかは、本件事業の運営に関する諸状況を総合的に勘案して初めて明らかにできる事柄であるから、本件各修正申告書等に係る錯誤が客観的に明白であるとはいえない。また、税理士の誤った説明を信じたことは法の不知に起因するものであることから、更正の請求以外の方法による是正を認めなければならないほどの重大な錯誤とはいえない。そうすると、本件各修正申告書等の記載内容に係る錯誤が、客観的に明白かつ重大であるということはできないので、本件においては、請求人による錯誤の主張を許すことはできない。以上によると、本件各賦課決定処分は、本件各修正申告書等が錯誤に基づくものであることを理由として、取り消されることにはならない。(令6. 1. 9 大裁(所・諸)令5-23)
請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する事実の隠蔽又は仮装行為があったか否かについては、請求人が関わっていた事業(本件事業)の事業主は、請求人ではないと認められることから、本件事業に係る所得は請求人に帰属しないし、本件事業に係る資産の譲渡等の対価を享受する者が請求人であるとは認められない。したがって、請求人において事実の隠蔽又は仮装行為があったとは認められない。(令6. 1. 9 大裁(所・諸)令5-23)
原処分庁は、請求人が関わっていた事業(本件事業)に係る所得は請求人に帰属すると主張する。しかしながら、本件事業を経営していると認められる者(事業主)が誰であるかという点は、実質所得者課税の原則を定めた所得税法第12条《実質所得者課税の原則》の趣旨に鑑み、事業許可等の名義のみならず、事業資産や事業資金の調達・管理、利益の管理・処分状況、従業員の雇用等事業の運営に関する諸状況を総合的に勘案して判定すべきであるところ、本件事業に係る売上げ及び経費の管理や利益金の処分状況、従業員の雇用並びに経営方針の決定等の状況からすると、本件事業の事業主は請求人ではなく、請求人と同居していた者であると認められ、請求人は、各種届出及び賃貸借契約等の単なる名義人であって、他の従業員と同程度の立場で本件事業に従事していたにすぎないというべきである。したがって、本件事業に係る所得は請求人に帰属せず、同様に、消費税等の課税期間の本件事業に係る資産の譲渡等の対価を享受する者も請求人であるとは認められない。(令6. 1. 9 大裁(所・諸)令5-23)
国税不服審判所裁決令和6年1月9日の抜粋です。黒塗り箇所は???としています。
事案の概要
デリバリーヘルス業(無店舗型性風俗特殊営業)に係る所得を記載した所得税等及び消費税等の確定申告書を提出していた審査請求人が、原処分庁の職員による調査に基づき修正申告書及び期限後申告書を提出したところ、原処分庁は無申告加算税及び重加算税の賦課決定処分を行った。また、請求人が、当該営業に係る所得は請求人に帰属しないとして所得税等及び消費税等に係る更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った。
これに対し、請求人は、無申告加算税及び重加算税の賦課決定処分と更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めるとともに、令和4年2月21日付でされたとする更正処分の全部の取消しを求めた。
所得税等の平成28年分から令和2年分までの各年分を併せて「本件各年分」といい、消費税等の各課税期間につきその暦年をもって表記し(例えば、平成30年1月1日から同年12月31日までの課税期間を「平成30年課税期間」という。)、平成30年課税期間から令和2年課税期間までの各課税期間を併せて「本件各課税期間」という。
基礎事実
請求人及び関係者について
請求人は、会社員として給与収入を得るほか、複数の名称を用いて、インターネット上の風俗情報サイトに広告を掲載するなどし、これを見た客からの電話による依頼を受けて女性スタッフを派遣し、当該女性スタッフが客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供してその対価を受領する、いわゆるデリバリーヘルス業に関わっていた。請求人が令和2年10月までの間に関わっていた当該デリバリーヘルス業を「本件デリヘル業」といい、客に対し役務を提供してその対価を受領する女性スタッフを「本件各デリヘル嬢」という。
本件デリヘル業に係る届出書の提出について
請求人は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、所轄警察署長に対して、複数の呼称を記載するなどした風営法第31条の2第2項の規定による無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出を請求人の名義で提出していた。
3 争点
本件における争点は、次の3点である。
争点1 本件デリヘル業に係る所得は請求人に帰属しないか否か
争点2 本件各賦課決定処分は、本件各修正申告等が請求人の錯誤に基づくものであること
を理由として取り消されるべきか否か
争点3 請求人について、通則法第68条第1項及び第2項に規定する事実の隠蔽又は仮装行
為があったか否か
4 本件デリヘル業に係る所得の帰属についての請求人の主張
請求人は、???が???であったため、本件デリヘル業の届出をすることができず、預金口座の開設、クレジットカードの作成も困難であったことから、これらの手続につき名義貸しをしたにすぎない。
請求人は、本件デリヘル業に係る日々の売上げや経費額をパソコンに入力すること、税務関係の資料を作成して税理士に渡すこと、広告の出し方を決めることなどに加え、平日夜や日曜日などに受付を手伝うことがあったが、毎日ではなく、請求人の本業である会社員として勤務をする傍ら、請求人の当時の妻の親族であった???のために???の事業の補助をしたにすぎず、行為としては単なる従業員のような役割にすぎなかった。
本件各デリヘル嬢の面接、採用は全て???が行っていた。その他、請求人名義の預金口座の入出金管理及び経費の支払を行っていたのも???であった。経費は、専ら請求人名義の1預金口座からの引落しであったが、当該口座の通帳及びキャッシュカードは常に???が持っていた。
本件デリヘル業から生ずる利益金(以下「本件利益金」という。)は全て???が受領しており、請求人は、本件利益金を一切取得していない。原処分庁は、請求人が???と同棲しており、???から生活費の一部を出してもらっていたこと、自動車等を買ってもらっていたこと等を理由に、請求人が本件デリヘル業に係る収益を享受していた旨主張する。
しかし、請求人は、当時、会社員として十分な給与収入を得ていたことから、本件利益金を生活の資とはしていない。請求人は、事業者である???の同居人として、???に生活費を一部負担してもらい、また、売上金に比較して僅かな物品(同期間で合計200万円強)を買い与えられただけであるにすぎず、収益を享受していたとはいえない
以上からすれば、本件デリヘル業の経営者として営業を支配管理し、その収益を自己に帰属させていたのは、請求人ではな???であり、本件デリヘル業に係る所得は???に帰属し、請求人は飽くまで単なる名義人であったにすぎない。したがって、本件デリヘル業に係る所得は、請求人に帰属しない。
5 審判所の判断
本件デリヘル業に係る所得の帰属について
本件デリヘル業の経営方針に関する重要事項について決定する権限を行使していたのは???であることなどからすれば、本件デリヘル業を経営していたのは、???であると認められ、請求人は、従属的な立場で本件デリヘル業に従事していたにすぎないというべきである。本件デリヘル業の事業主は、請求人ではなく、???であると認めるのが相当である。
本件デリヘル業が、請求人と???による共同事業であるとは認められない。
「イ 法令解釈
(イ)所得税法第12条は、所得が誰に帰属するかにつき、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であり、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属する旨規定し、いわゆる実質所得者課税の原則を定めており、その趣旨は、担税力に応じた公平な税負担を実現するため、収益の法形式上の帰属者(名義人)と法律的実質的帰属者が相違する場合、後者を収益の帰属者とするというものと解される。
これを受け、所得税基本通達12-2は、事業から生ずる収益を享受する者が誰であるかは、その事業を経営していると認められる者(事業主)が誰であるかにより判定するものとする旨定めており、また、同通達12-5は、生計を一にしている親族間における事業の事業主が誰であるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定についての支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する旨定めているところ、当審判所においても、これらの取扱いは所得税法第12条の趣旨を正しく解するものとして相当と認められる。
そして、その事業を経営していると認められる者(事業主)が誰であるかという点は、実質所得者課税の原則を定めた所得税法第12条の趣旨に鑑み、事業許可等の名義のみならず、事業資産や事業資金の調達・管理、利益の管理・処分状況、従業員の雇用等事業の運営に関する諸状況を総合的に勘案して判定すべきである。
(ロ)また、消費税法第13条も、法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、同法を適用する旨規定しており、所得税法と同様の実質課税の原則を規定したものと解されるから、その事業に係る資産の譲渡等の対価を享受する者が誰であるかという点は、上記(イ)と同様に判定すべきものと解される。」
共同事業の可能性について
「 一般に、所得を生ずる原因となる経済活動を二人以上の者が共同して行ったといえるためには、所得税法の趣旨、目的に照らし、その経済活動による経済力の獲得又は増加をそれらの者がそれぞれ支配していることを必要とし、これらの者が自己の計算と危険において主体的に経済活動を行っていることが必要であって、単にその活動に何らかの形で関与すれば足りるというものではない。したがって、共同事業と認められるためには、当該経済活動を行うことについて相互に意思の連絡があり、その意思決定に各人が主体的に関与するとともに、これを各人が主体的に実現するため
にそれぞれ分担又は役割を遂行することが不可欠である上、その活動の結果生じた所得に対する各人の持分割合が当該意思決定の中で定められ、これを合理的に算出できる場合でなければならないと解するのが相当である。」
「 これを本件についてみると、・・・自己の計算と危険において主体的に本件デリヘル業を行っていたのは???であり、請求人は、本件デリヘル業に関して従属的な役割を有していたにすぎず、また、本件デリヘル業により生じた所得については、???が全て取得することとされており、請求人は持分を得てはいない。」
本件各賦課決定処分は、本件各修正申告等が請求人の錯誤に基づくものであることを理由として取り消されるべきか否か。)について
本件各賦課決定処分は、本件各修正申告等が錯誤に基づくものであることを理由として、取り消されることにはならない。
「イ 法令解釈
所得税等及び消費税等については、納付すべき税額を納税者の申告により確定することを原則とする申告納税方式が採用されている。そして、このような申告納税方式に係る国税については、納税申告書を提出した者は、当該納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき等には、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る税額等を更正すべき旨を請求することができると規定されている(通則法第23条《更正の請求》第1項)。
通則法がこのように納税申告書記載事項の過誤の是正につき特別の規定を設けているのは、申告納税方式に係る国税の課税標準等の決定については、最もその事情に通じている納税義務者自身の申告に基づくものとし、その過誤の是正は法律が特に認めた場合に限るとすることが、租税債務を早期に確定させるという国家財政上の要請に応じつつ、納税義務者に対して過大な不利益を強いることにならない点で適当と認めたためと解される。
そうすると、納税申告書の記載内容の過誤の是正については、原則として更正の請求によるべきであり、これによらずに記載内容の錯誤を主張することが許されるのは、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、更正の請求以外にその是正を許さないとすると納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限られるというべきである(最高裁判所昭和39年10月22日第一小法廷判決・民集18巻8号1762頁参照)。
ロ検討
請求人は、上記3の(2)の「請求人」欄のとおり、本件デリヘル業に係る所得は請求人に帰属せず、また、本件各修正申告書等については、???の「税金が発生したとしても、破産をすれば支払わなくてよい」という誤った説明を請求人が信じて錯誤に陥ったことにより提出したものであり、そして、本件各修正申告等によって請求人が負担する税額が多額であることも併せ考えると、その錯誤
は客観的に明白かつ重大であって、法定の方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害するというべきである旨主張する。
この点、本件デリヘル業に係る所得が請求人に帰属しないことは上記(2)で説示したとおりであり、請求人が本件各修正申告書等を提出するに際して、本件デリヘル業に係る所得の帰属について誤った認識を有していた(錯誤に陥っていた)可能性はある。しかしながら、上記イで説示したとおり、本件各修正申告書等の記載内容の過誤の是正については、原則として更正の請求によるべきであり、これによらずに記載内容の錯誤を主張することが許されるのは、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、更正の請求以外にその是正を許さないとすると納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限られるというべきである。そして、本件デリヘル業から生ずる収益を享受する者が誰であるかは、上記(2)のイの(イ)で説示したように、本件デリヘル業の運営に関する諸状況を総合的に勘案して初めて明らかにできる事柄であることからすると、本件各修正申告書等の記載内容に係る錯誤が客観的に明白であったとはいい難い。
また、請求人は、一の上記のような誤った説明によって錯誤に陥った旨主張するものの、請求人がこのような説明を信じたことは、法の不知に起因するものであることからすれば、その錯誤は、更正の請求以外の方法による是正を認めなければならないほど重大なものということはできない。
そうすると、本件各修正申告書等の記載内容に係る錯誤が、客観的に明白かつ重大であるということはできないので、本件においては、請求人による錯誤の主張を許すことはできないといわざるを得ない。以上によると、本件各賦課決定処分は、本件各修正申告等が錯誤に基づくものであることを理由として、取り消されることにはならない。」
原処分の適法性について
「イ 本件各通知処分の適法性について
上記(2)のとおり、本件デリヘル業に係る所得は請求人に帰属せず、同様に本件デリヘル業に係る資産の譲渡等に係る対価を享受する者も請求人であるとは認められないから、本件各更正請求は理由がある。ただし、平成29年分、平成30年分及び令和元年分の所得税等の各更正の請求については、納付すべき税額の計算に誤りがある。
したがって、本件各通知処分のうち、平成29年分、平成30年分及び令和元年分の所得税等の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分は、いずれもその一部を別紙2から別紙4までの各「取消額等計算書」のとおり取り消すべきであり、それ以外の本件各通知処分は、いずれもその全部を取り
消すべきである。
ロ 平成30年課税期間の消費税等の無申告加算税の賦課決定処分の適法性について
上記イのとおり、平成30年課税期間の消昔税等の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部が取り消されることにより、平成30年課税期間の消費税等の納付すべき税額が???となるから、 平成30年課税期間の消費税等の無申告加算税の賦課決定処分は、その全部を取り消すべきである。
ハ 重加算税の各賦課決定処分の適法性について
(イ)上記(4)のとおり、請求人において、通則法第68条第1項及び第2項に規定する事実の隠蔽又は仮装行為があったとは認められないから、重加算税を賦課することはできない。さらに、上記イのとおり、本件各通知処分は、いずれも全部又は一部を取り消すべきであるから、令和2年分を除く本件更正請求各年分の所得税等の納付すべき税額は別紙2から別紙4までの各「取消額等計算書」の「4 課税標準等及び税額等の計算」欄の各金額のとおりであり、また、令和元年課税期間の消費税等の納付すべき税額は???となって、いずれも確定申告額(なお、令和元年分の所得税等については更正処分額)を下回り、期限後申告となった平成30年課税期間及び令和2年課税期間の消費税等の納付すべき税額も???そうすると、令和2 年分を除く本件更正請求各年分の所得税等及び本件各課税期間の消費税等については、いずれも加算税の基礎とな
る税額が???となる。・・・じたがって、本件更正請求各年分の所得税等に係る重加算税の各賦課決定処
分及び本件各課税期間の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分は、いずれもその全部を取り消すべきである。
(ロ) 上記(イ)の各処分以外の更正の請求がなされていない年分である平成28年分の
所得税等に係る重加算税の賦課決定処分も、上記(4)のとおり、請求人において、通則法第68条第1項に規定する事実の隠蔽又は仮装行為があったとは認められないから、重加算税を賦課することはできない。
もっとも、上記(3)のとおり、平成28年分の所得税等に係る修正申告書を含む本件各修正申告等は錯誤に基づくものではなく有効であり、そして、当審判所の調査及び審理の結果によっても、平成28年分の所得税等に係る修正申告により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が当該修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があるとは認められない。そうすると、平成28年分の所得税等に係る重加算税の賦課決定処分は、平成28年分の所得税等に係る修正申告により納付すべき税額を基礎として計算された過少申告加算税に相当する額の限度で適法であると認められる。
したがって、平成28年分の所得税等に係る重加算税の賦課決定処分は、上記過少申告加算税に相当する額を超える部分が違法であるから、その一部を別紙1の「取消額等計算書」のとおり取り消すべきである。」
「よって、令和4年2月24日付及び令和5年4月17日付でされた各処分の取消しを求める審査請求は上記(5)の限度で理由があるから、上記・・・のとおり原処分の一部を取り消すこととし、また、令和4年2月21日付でされたとする平成28年分の所得税等に係る更正処分の取消しを求める審査請求は不適法なものであるからこれを却下することとして、主文のとおり裁決する。」
ダウンロード資料
同日付の別事案の裁決
審判所のホームページ掲載の裁決要旨
原処分庁は、請求人が関わっていた事業(本件事業)に係る所得は請求人に帰属すると主張する。しかしながら、本件事業を経営していると認められる者(事業主)が誰であるかという点は、実質所得者課税の原則を定めた所得税法第12条《実質所得者課税の原則》の趣旨に鑑み、事業許可等の名義のみならず、事業資産や事業資金の調達・管理、利益の管理・処分状況、従業員の雇用等事業の運営に関する諸状況を総合的に勘案して判定すべきであるところ、本件事業に係る売上げ及び経費の管理や利益金の処分状況、従業員の雇用並びに経営方針の決定等の状況からすると、本件事業の事業主は請求人ではなく、請求人と同居していた者であると認められ、請求人は、各種届出及び賃貸借契約等の単なる名義人であって、他の従業員と同程度の立場で本件事業に従事していたにすぎないというべきである。したがって、本件事業に係る所得は請求人に帰属せず、同様に、消費税等の課税期間の本件事業に係る資産の譲渡等の対価を享受する者も請求人であるとは認められない。(令6. 1. 9 大裁(所・諸)令5-23)
デリヘル・風俗業の税金で知っておくべき基本
デリヘル(デリバリーヘルス)をはじめとする風俗業の税金は、一般的な事業と異なる点がいくつかあります。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく無店舗型性風俗特殊営業は、適法な届出のもとで運営される事業である以上、所得税・消費税の申告義務は当然に生じます。「風俗業だから申告しなくてよい」という誤解は厳禁です。
風俗業の所得はどのように計算するか
デリヘルなどの風俗業で得た収入は、事業所得として確定申告が必要です。売上(客からの料金収入)から、広告費・人件費(女性スタッフへの報酬)・通信費・その他の経費を差し引いた所得に対して所得税が課されます。また、課税売上高が1,000万円を超える場合は消費税の申告・納付も必要となります。
名義貸しと実質所得者課税の原則
本裁決が示すように、デリヘル業においては「名義貸し」が問題となるケースがあります。風営法上の届出や口座を他人名義で行っても、実際に事業を経営して利益を享受している者が「実質的な事業主」として課税されます。これが所得税法第12条に規定する「実質所得者課税の原則」です。名義を貸した側が税務署から納税を求められるリスクがあるため、安易な名義貸しは避けるべきです。
デリヘル・風俗業が税務調査の対象になりやすい理由
風俗業の税金に関して、税務署は特に注意を払っています。デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業は、現金取引が多く、売上の把握が困難なケースがあるためです。さらに、以下のような点が税務調査の端緒となりやすいとされています。
- 申告所得と生活実態(支出・資産)が乖離している場合
- 風営法上の届出が提出されているにもかかわらず所得申告がない場合
- インターネット上の風俗情報サイトへの広告掲載が確認できる場合
- 関係者(女性スタッフ等)の情報から事業実態が把握された場合
本裁決の請求人も、インターネット上の風俗情報サイトへの広告掲載が税務署による調査の手がかりのひとつとなっていました。デジタル化の進展により、税務署のデータ収集・分析能力は年々高度化しており、申告漏れのリスクは高まっています。
税務調査・裁決事例の活用|税理士による専門サポート
実質所得者課税の原則をはじめ、税務調査・不服申立ての実務では裁決事例の分析が重要です。泉絢也税理士事務所では所得税・法人税・相続税など幅広い税務問題に対応しています。
税務でお困りの方へ|税理士にご相談ください
以下のようなお悩みがある方は、ぜひご相談ください。全国対応しています。
- 暗号資産・仮想通貨の税務調査に対応したい
- 暗号資産の売却・交換・マイニング等に係る課税関係を整理したい
- 確定申告・修正申告について専門家のサポートを受けたい
- 所得税・法人税・相続税など幅広い税務問題について相談したい
高度な損益計算については、カオーリア会計事務所(https://kaoria-tax.com/)と提携して対応しています。
デリヘル・風俗業の税金に関するよくある質問(FAQ)
デリヘルなどの風俗業の収入は確定申告が必要ですか?
はい、必要です。デリヘルをはじめとする風俗業の事業収入は、所得税法上の事業所得に該当します。給与所得等との合算を含め、毎年3月15日までに確定申告を行う必要があります。申告を怠ると、無申告加算税(15〜30%)や延滞税が課されるほか、悪質な場合には重加算税(35〜40%)の対象にもなります。
デリヘル事業の名義を貸した場合、税金はどうなりますか?
名義を貸した者が税金を課される可能性があります。ただし、本裁決が示すように、実質的に事業を経営して利益を享受していた者が「実質的な事業主」として課税されます。名義人であっても、売上管理・経費管理・従業員の雇用・経営方針の決定等に関与していた場合は、事業主と認定されるリスクがあります。名義貸しのトラブルに巻き込まれた場合は、速やかに税理士にご相談ください。
デリヘル・風俗業で修正申告を提出した後に取り消せますか?
原則として、修正申告の取消しは困難です。本裁決においても、「錯誤に基づく修正申告の取消し」は認められませんでした。申告内容に誤りがある場合の正規の是正手段は「更正の請求」(法定申告期限から原則5年以内)です。税務調査の際に提示された修正申告書に安易に署名・押印することは避け、内容を十分に確認した上で対応することが重要です。
風俗業の税務調査を受けた場合、重加算税を避けられますか?
重加算税は「事実の隠蔽または仮装」があった場合に課されます(国税通則法第68条)。本裁決では、名義人である請求人に隠蔽・仮装行為があったとは認められず、重加算税の取消しが認められました。一方で、売上を意図的に隠したり、架空の経費を計上したりした場合は重加算税が課されます。適切な申告と誠実な対応が重加算税回避の基本です。
デリヘルなどの風俗業に詳しい税理士に相談すべきですか?
はい、強くお勧めします。風俗業の税金は、名義問題・現金売上の管理・源泉徴収・消費税など複雑な論点を含みます。また、税務調査の対象になりやすい業種でもあります。税務調査の通知を受けた際は、税理士を代理人として立てることで、不当な課税処分を防ぐことができます。当事務所では、風俗業・デリヘルの税金・税務調査対応についてのご相談も承っております。