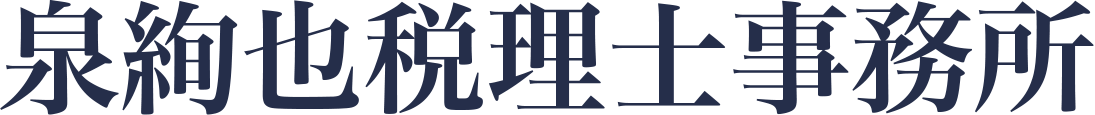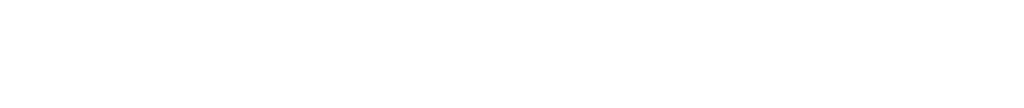記事の紹介:令和7年度、国税庁は「税理士事務の運営に当たり特に留意すべき事項について(指示)」を全国の国税局・税務署に発出しました。
この指示は、税理士制度の信頼確保を目的に、税理士法違反の未然防止、にせ税理士への対応、税理士会との連絡協調、職員研修の充実など、国税庁の税理士事務運営の基本方針を定めた重要な文書です。
特に本年度は、
- 税理士による不正関与への情報収集・通報(税理士等情報せん)の徹底、
- e-Tax・キャッシュレス納付、デジタルシームレス化などのDX施策との連携、
- 懲戒逃れや無資格業務(にせ税理士)への厳正対応、
- 退職予定職員への税理士法第42条(業務制限)説明の徹底
など、実務現場に大きく関わる具体策が強調されています。
令 和 7 年 6 月 2 4日
各 国 税 局 長 殿
沖縄国税事務所長
国税庁 長 官
(官 印 省 略)
令和7事務年度における税理士事務の運営に当たり特に留意すべき事項について(指示)
標題のことについては、別紙のとおり定めたから、平成 14 年7月5日付官総6-110「『税理士事務提要』の制定について」(事務運営指針。以下「提要」という。)及び令和7年6月 19 日付官総 10-28 ほか 32 課共同「令和7事務年度における事務運営に当たり特に留意すべき各事務系統に共通する事項について」(指示)によるほか、これにより適切な運営を図られたい。
別紙
1 基本的な考え方
国税庁の任務の一つである「税理士業務の適正な運営の確保」とは、公共的使命を負う税理士及び税理士法人(以下「税理士等」という。)が申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重要な役割を果たすよう、税理士の業務が適正に行われることを確保することである。
税理士事務は、国税庁のこの任務を遂行するために行うものであり、職員は、その重要性を認識した上で、税理士法をはじめとする関係法令や提要等に基づき、「税理士会(支部を含む。以下同じ。)との連絡協調」、「税理士等に対する指導監督等」などに取り組む。税理士事務の運営に当たっては、PDCAサイクルに基づき、取組状況を適切に分析・ 評価した上で、取組方法の改善など必要な対応を行うとともに、庁局署間で連携しながら、効果的かつ効率的な運営に努める。
また、各取組に当たっては、局署の実情を踏まえ、十分な事務量の確保と適切な事務量 配分をした事務計画の策定を行う。急な欠員などが生じた場合には、必要に応じて事務処 理体制の変更や事務計画の見直しを行うなど、適切な進行管理と弾力的な運営に配意する。
参考:提要第1章第3節〈1 税理士事務運営に当たって〉
2 税理士法に関する職員研修等の実施
税理士事務の実施に当たっては、局署の職員が、税理士法や関係通達などに関する知識を正しく習得する必要がある。
このため、局署においては、事務年度首の早い段階で、職員に対して、税理士会との連絡協調に必要な知識や「税理士等情報せん」の作成に必要な税理士法違反行為の基礎的知識などに関する職員研修等を確実に実施する。
※ 「税理士等情報せん」は、平成14 年6月28 日付官総6-106 ほか12 課共同「関係各部課及び税務署から税理士監理官への情報提供要領の制定について」(事務運営指針。以下「情報提供要領通達」という。)に定めるものをいう。
【職員研修等に盛り込む内容】
- 税理士等の自己脱税や無申告が見込まれる事案は、課税調査の対象として確実に選定すること。
- 課税調査や滞納整理など(以下「課税調査等」という。)の過程において、多額の不正行為の事実を把握したときは、課税調査等の担当者は、税理士等の不正関与の有無を必ず確認すること。
- 確認の結果、税理士等の不正関与の疑いがある場合には、税理士監理官へ速やかに連絡するとともに、「税理士等情報せん」を作成すること。
- 税理士による調査妨害などが疑われる行為を把握した場合は、課税調査等の担当者は、直ちに具体的な事実に基づく当該行為の詳細(日時、場所、当方及び相手方の言動に関する具体的事実など)について、確実に記録に残すこと。
参考:提要第1章第3節〈2 税理士法等に関する職員研修等の実施〉
3 税理士会との連絡協調
申告納税制度の適正かつ円滑な運営を図る上で、公共的使命を担う税理士等が果たすべき役割は極めて大きなものがあることから、税務行政に対する税理士等の理解を得ることが重要である。
このため、局署幹部は、日頃からあらゆる機会を通じて、税理士会役員等と意思疎通を図り、税理士会との連絡協調を推進する。
⑴ 税理士会との連絡協議会等の開催
局署幹部は、税理士会との連絡協議会等を通じ、幅広い課題について協議・意見交換を行うなど、税理士会との連絡協調に努める。
なお、e-Tax・キャッシュレス納付の利用拡大や、取引から会計・税務までのデジタル化(デジタルシームレス)といった事業者のデジタル化促進などのDX関連施策のほか、書面添付制度の一層の普及・定着など、税理士等の業務と密接に関係した税務行政の各種施策の実施に当たっては、税理士等の要望を的確に把握するとともに、施策への理解を求める。
⑵ 税理士会が開催する研修会等への講師派遣
税理士会が開催する研修会等への講師派遣の要請があった場合には、積極的に協力する。
講師派遣に当たっては、税理士会の要望をよく把握した上で、過去の評価等を踏まえて資料の見直しを行うなど、税理士の理解向上に向けて研修内容の充実を図る。
参考:提要第2章第1節〈1 協議会等の開催〉、〈3 研修会等への協力〉
4 税理士等に対する指導監督・にせ税理士への対応
税理士等に対する指導監督の的確な実施や、税理士等でない者による税理士法第52 条、第 53 条違反行為(以下当該行為者を「にせ税理士」という。)への厳正な対処のため、以下の項目に重点的に取り組む。
⑴ 税理士等による税理士法違反行為の未然防止
税理士制度に対する国民の信頼を確保するためには、税理士等による税理士法違反行為の未然防止を図ることが肝要である。
このため、局署幹部は、税理士法違反行為の未然防止の重要性を十分に認識し、税理士会との会合や協議会・研修会、実態確認(税理士)等のあらゆる機会を活用して、積極的・効果的な注意喚起を行う。
⑵ 「税理士等情報せん」の的確な収集等
税理士等に対する指導監督やにせ税理士への対応を的確に行うためには、税理士法違反行為に関する情報の収集が不可欠である。
このため、税理士等に対する指導監督事務を所掌している税理士事務担当者は、自ら率先して、税理士法違反行為の情報収集に努める。
参考:提要第3章第1節〈1 情報せんの作成等〉
⑶ 課税調査等の担当者との意識共有等
局署職員は、情報提供要領通達に基づき、適切に「税理士等情報せん」を作成し、税理士監理官に提出する。特に、課税調査等において、脱税相談、不真正税務書類の作成、自己脱税、自己申告漏れ、調査妨害といった悪質な税理士法違反行為が疑われる事実等を把握した場合は、税理士監理官に速やかに連絡する。
その場合、税理士事務担当者との間で、課税調査等や税理士法違反行為に係る調査の処理方針等について意識共有を図るとともに、税理士法違反行為に関する証拠資料の収集と保全を確実に行う。
⑷ 税理士等に対する実態確認
実態確認(税理士)は、署税理士事務担当者が主体となって、次の点に留意して、計画的かつ的確に実施する。
イ 必要事務量の確保
署幹部は、署税理士事務担当者が実態確認(税理士)に必要な事務量を確保できるよう、適切な管理を行う。
ロ 対象者の選定
署税理士事務担当者は、各種情報や部内簿書等に基づき、実態確認(税理士)の対象者を的確に選定する。その際、税理士自身の無申告や申告漏れ等により懲戒処分や指導を受けた税理士等については、じ後の申告状況を確実に確認する。
ハ 実態確認(税理士)の実施
実態確認(税理士)については、書面照会と電話・資料徴求による接触を基本としつつ、必要に応じて書面照会を行わずに臨場するなど、事案に応じた適切な接触方法を選択することにより、効果的・効率的な実施に努める。
なお、対象者の関与先数や事務所の規模等、署担当者の経験等を勘案して、適宜、税理士専門官や税理士事務専門官(以下「税理士専門官等」という。)による支援・指導を行う。
実態確認(税理士)の実施の際、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19年法律第 22 号)の遵守状況については、税理士の責務の認識や特定受任行為の代理等の有無を必ず確認し、状況に応じて、指導や注意喚起を適切に行う。
参考:提要第4章第1節〈3 選定〉、〈4 計画及び進行管理等〉、〈5 実施要領〉
⑸ 税理士等に対する税理士法上の調査
税理士等に関する情報等から税理士法違反行為があると認められる場合には、税理士
に対する懲戒処分や税理士法人に対する処分を視野に入れ、次の点に留意して税理士法上の調査(以下「調査」という。)を実施する。
なお、事務年度中に争訟事案が発生した場合には、調査計画を変更するなどして、争訟事案に対応するための事務量を確保する。
イ 調査対象者の選定
税理士法違反行為が放置されることのないよう、次の重点調査対象事案のほか、複雑・困難事案を調査対象として的確に選定する。
なお、税理士監理官が、税理士等自身の無申告情報を把握した場合には、局内関係課と税理士等に関する課税調査の実施について協議する。
【重点調査対象事案】
- 故意による不真正税務書類の作成等(税理士法第 45 条第1項該当)
- 税理士等自身(税理士が代表者である法人又は実質的に支配していると認められる法人を含む。)の脱税(税理士法第 37 条違反)
- 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ(無申告に係るもの)(税理士法第 37 条違反)
- 調査妨害(税理士法第 37 条違反)
- 業務け怠(委嘱された税理士業務について正当な理由なく怠ったことをいう。)(税理士法第 37 条違反)
ロ 調査の実施
調査の実施に当たっては、じ後の不服申立て等を念頭において、事実関係を的確に把握するとともに、証拠資料の収集及び保全を確実に行い、処分の適法性の確保に努める。
なお、調査によって懲戒処分等に相当する違反行為が把握された場合には、調査過程の早い段階で庁担当者と相談し、処理方針の検討を行う。
参考:提要第4章第2節〈2 選定〉、〈5 調査着手の要領〉、〈7 実施に当たっての留意事項〉
ハ 懲戒逃れを図る者への対応
令和5年4月1日以後に行われた調査の過程で懲戒処分を逃れる目的で税理士を自主廃業する者(いわゆる、懲戒逃れを図る者)については、税理士法第 48 条の「懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等」の適用を検討し、税理士法第 55条第2項(監督上の措置)により調査を継続する。
なお、令和5年3月 31 日以前に行われた調査の過程で懲戒逃れを図る者については、上記の適用がないことから、国税当局として個別管理を徹底する。
参考:提要第4章第2節〈1 対象者〉、〈7 実施に当たっての留意事項〉、第6章第2節〈2
懲戒処分等を受けた者等へのフォローアップ〉
⑹ にせ税理士に対する実態確認等イ 実態確認(非税理士)
次の対象者を含め、にせ税理士行為が想定される者については、実態確認(非税理士)の対象者として確実に選定する。
- 「税理士業務の禁止」の処分を受け、その処分期間中の者
- 令和5年3月 31 日以前に行われた税理士法違反行為に係る調査の過程において懲戒逃れを図った者
- 税理士法第 48 条(懲戒処分を受けるべきであったことについての決定等)の規定による決定を受けた者
- 税理士法第 37 条の2(非税理士に対する名義貸しの禁止)の規定に違反する行為を行っている者の名義を利用している者
実態確認(非税理士)については、臨場による接触以外にも、事案に応じて書面照会や電話による接触を選択するなど、効果的かつ効率的な実施に努める。
また、告発を見据えた対象者については、対象者の決定、警察当局との事前協議などの各時点において、庁担当者と情報共有を行う。
ロ 命令制度に係る調査
にせ税理士が不審な内容の税務相談を行っている情報を把握した場合には、確実に命令制度に係る調査の対象者として選定する。
局担当者は、命令制度に係る調査を実施する場合、当面の間、事前に庁担当者に連絡をする。
参考:提要第7章第3節〈2 選定〉、〈5 実態確認(非税理士)の実施〉、〈6 実態確認時の留
意事項〉、第4節<2 選定>、<4 調査着手>、<5 調査実施に当たっての留意事項>
5 退職予定職員に対する注意喚起等の徹底
局署幹部は、税務職員を退職して税理士となる者に対し、退職予定職員に対する説明会などの機会を利用し、税理士法について説明する。
特に、税理士法第 42 条(業務の制限)は、税務行政に従事していた者に課せられた制限であることから、税理士業務の制限の対象となる基本的な範囲など、留意すべき内容等を確実に周知徹底し、税理士法違反行為の未然防止を図る。
関連記事
参考資料(ダウンロード可)
令和7年6月24日付官税1ー72ほか15課共同「令和7事務年度における税理士関係事務の運営に当たり特に留意すべき事項について」(指示).pdf