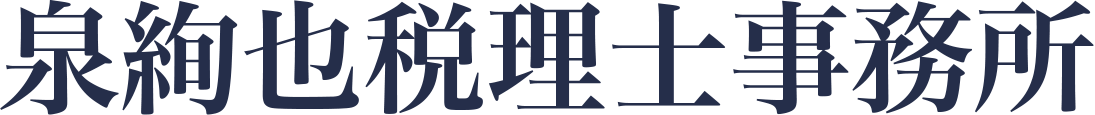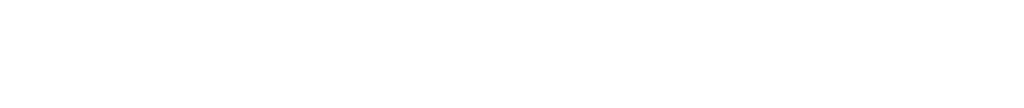国税庁の税務大学校のホームページに論文を掲載していただきました。
「暗号資産(仮想通貨)の税務調査と税務執行上の課題-ブロックチェーン分析と損益計算の重要性-」
結構分量がある論文なので、どんなことを書いたかを簡単に説明しておきます。必ずしも原文の構成どおりの説明ではないのでご注意ください。
論文では、暗号資産の税務執行における課題と対応策について検討しています。
要するに、暗号資産の匿名性、分散性、損益計算の困難性が税務執行に与える課題と考えられる対応策について、他国や日本の現状を踏まえて考察を進めています。
第Ⅱ章:暗号資産の匿名性と分散性が引き起こす税務執行の課題
暗号資産の匿名性と分散性は、税務執行においてさまざまな問題を引き起こします。
1. 匿名性による問題
暗号資産の匿名性により、税務当局はブロックチェーン上の取引を把握していても、取引の当事者を特定することが困難です。また、特定の納税者がどのような暗号資産を保有し、取引しているのかを把握することも難しいです。これにより、以下のような問題が生じます。
- 自国での納税義務の有無や所得金額の確認ができない。
- 自国の居住者が行う暗号資産の利用状況や税務コンプライアンスの実態を把握できない。
2. 分散性による問題
暗号資産の分散性により、従来の税務執行の枠組みが機能しにくくなっています。税務当局は通常、企業や金融機関などの中央集権的な機関を通じて情報を収集しますが、完全な分散型システムでは「仲介者」が存在しないため、情報提供や源泉徴収を担う主体がいません。
一方、中央集権型の取引所(CEX)が取引の中心的な役割を担うようになり、匿名性や分散性が一部弱まった面もあります。しかし、分散型金融(DeFi)や分散型取引所(DEX)の登場により、仲介者を介さないピアツーピアの取引が増加し、分散性が強化されました。これが匿名性を補完し、両者は相互に関連しながら発展しています。
3. 税務コンプライアンスへの影響
暗号資産の匿名性と分散性は、税務コンプライアンス意識の低い納税者に有利な環境を提供します。これは、課税の透明性を高めるための国際的な取り組みを脅かす重大なリスクです。このような背景から、OECDは暗号資産報告枠組み(CARF)を策定しました。しかし、以下のようなケースではCARFが十分に機能しない場合があります。
- CARFに参加していない国のCEXを利用する場合。
- 報告義務者(RCASP)に該当しないDEXやプライベートウォレットを利用する場合。
4. 日本における課題
日本でも、暗号資産の匿名性と分散性が税務執行に影響を与えています。海外のCEXやDEX、プライベートウォレットを利用した取引では、本人確認が行われていない場合が多く、国税庁が取引を捕捉しても、以下のような問題が生じます。
- 口座やウォレットの管理者や所有者を特定することが困難。
- 特定の納税者(例えば、現在、税務調査中の納税者)がそのような口座やウォレットを利用している事実を把握することが難しい。
質問検査権やCARF、特定事業者への情報提供の求めといった制度は、国内やCARF参加国に情報提供義務を負う主体が存在する場合にのみ有効です。しかし、海外のCEX(特にCARF非参加国)、DEX、プライベートウォレットを利用する納税者の情報を国税庁が把握することは非常に困難です。
第Ⅲ章:ブロックチェーン分析
暗号資産の税務執行における課題に対応するため、ブロックチェーン分析が有効な調査手法として注目されています。国税庁は高性能なブロックチェーン分析ツールを積極的に活用し、調査官のトレーニングを強化する必要があります。
1. ブロックチェーン分析の限界
ブロックチェーン分析は、本人確認を行っていないCEXの口座やプライベートウォレットの管理者を直接特定することはできません。特に、納税者が本人確認済みのCEXとのつながりを持たない場合、特定はほぼ不可能です。このため、CEXが本人確認を実施していることや、納税者がそのようなCEXを利用していることが、税務執行の適正化に重要です。
2. ブロックチェーン分析への期待
一方、以下の場合にはブロックチェーン分析が有効に機能する可能性があります。
- 本人確認を行っていないCEXの口座やウォレットアドレスが、本人確認済みのCEXと取引を行った場合、その管理者を特定できる可能性がある。
- 特定されたアドレスに関連する暗号資産の取引や残高、同一人物が管理する口座やウォレットを把握できる。
チェイナリシス社が提供するようなブロックチェーン分析のツールやサービスを活用することにより、納税者の特定やDEXでの取引の把握が容易になる場合があります。
注意すべきことに、DEXの取引はブロックチェーン上に公開されているため、税務当局が確認可能です。一方、CEXの内部取引は外部から見るとブラックボックスであり、納税者やCEXの協力がない限り詳細を確認することはできません。
第Ⅳ章・結びに代えて:損益計算の困難性による税務執行の課題
暗号資産の税務執行において、損益計算の困難性が最も深刻な課題の一つです。この問題により、国税庁は調査対象の選定や課税処分を効率的に行えない場合があります。
1. 損益計算の難しさ
損益計算ソフトを使用しても、暗号資産の損益計算は複雑です。特に、海外CEX、DEX、複数のプライベートウォレットを利用する場合、正確な計算は困難です。その原因は以下の通りです。
- データの取得ができない場合がある。
- データを損益計算ソフトに適切に取り込めない場合がある。
- 年末数量の不一致(理論値と実際の数量の差)を適切に解消するのが難しい場合がある。
- 損益計上の有無やタイミングの判断が難しい場合がある。
2. 情報の非対称性
暗号資産の取引では、納税者は自身の取引状況を把握していますが、税務当局は十分な情報を得られません。この「情報の非対称性」が特に顕著です。従来、税務当局は「納税者の取引内容を知らない」ことが課題でしたが、暗号資産では「トランザクションの記録は分かっているが、納税者が誰か分からない、取引内容が分からない、損益計算を「正確に」行うことができない。」ケースも珍しくありません。要するに、次のような問題が生じています。
- 納税者自身も取引や損益の詳細を正確に把握できない場合がある。
- 税務当局が取引データを入手しても、取引主体や内容を特定できない。
- 取引主体を特定できても、正確な損益計算ができない。
3.対応策の提案
暗号資産の税務執行の適正性と公平性を確保するため、以下のような対応策が求められます。
(1)納税者への働きかけ
納税者がコントロール可能な要素について、適正な申告を促す取り組みが必要です。例えば、以下のような行動が実行されるような政策を検討すべきです。
- 取引する暗号資産やCEX、ウォレットの選択を慎重に行う。
- 取引履歴やデータの記録・保存を徹底する。
- データの定期的なダウンロードやバックアップを行う。
(2)ブロックチェーン分析と損益計算ソフトの活用
国税庁は、ブロックチェーン分析ツールや損益計算ソフトを積極的に活用し、調査手法の開発や調査官のトレーニングを進める必要があります。チェイナリシス社などブロックチェーン分析の専門業者との連携も重要です。
(3)制度の拡充
以下の制度的な対応も検討すべきです。
- 国税庁の通達やFAQの充実。
- 暗号資産の譲渡原価の簡便な算定方法の導入。
- CARFの改訂や参加国の拡大。
- 国内の情報提供制度の強化。
- 納税者にCEXやウォレットの情報提出を義務付ける、または促す仕組み。
(4)分離課税導入時の対応
暗号資産取引の所得に分離課税を導入する場合、以下のような条件を設けることが考えられます。
- 国内CEXや本人確認済みのCEXを通じた取引に限定する。
- 一定の性能を持つ損益計算ソフトで作成したデータを提出する場合に限定する。
4. 規制強化とその影響
規制強化により、納税者が規制の緩い国やプラットフォームに移行する可能性があります。この動きを注視し、適切な対策を講じる必要があります。
5. プライバシーと税務調査のバランス
インターネットやブロックチェーン上の公開情報を活用して納税者を特定する手法は有効ですが、プライバシーに関する懸念も生じます。国税庁によるAI技術やスクレイピングの利活用の状況も考慮したうえで、プライバシー保護等との関係で、今後さらなる議論が必要です。
まとめ
暗号資産の匿名性、分散性、損益計算の困難性は、税務執行に大きな課題をもたらします。
納税者に一方的な負担を強いるのではなく、納税環境の整備やテクノロジーの活用を通じて、適正かつ公平な税務執行を実現することが重要です。
国税庁は、急速に進化するテクノロジーに対応するために、テクノロジーを活用した調査手法の開発や専門性の向上を進める必要があります。