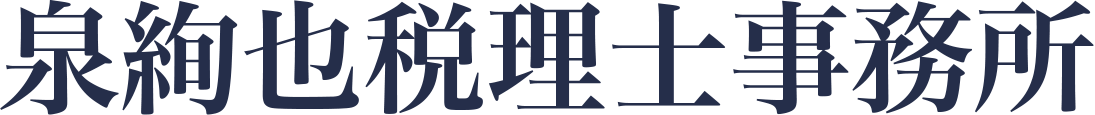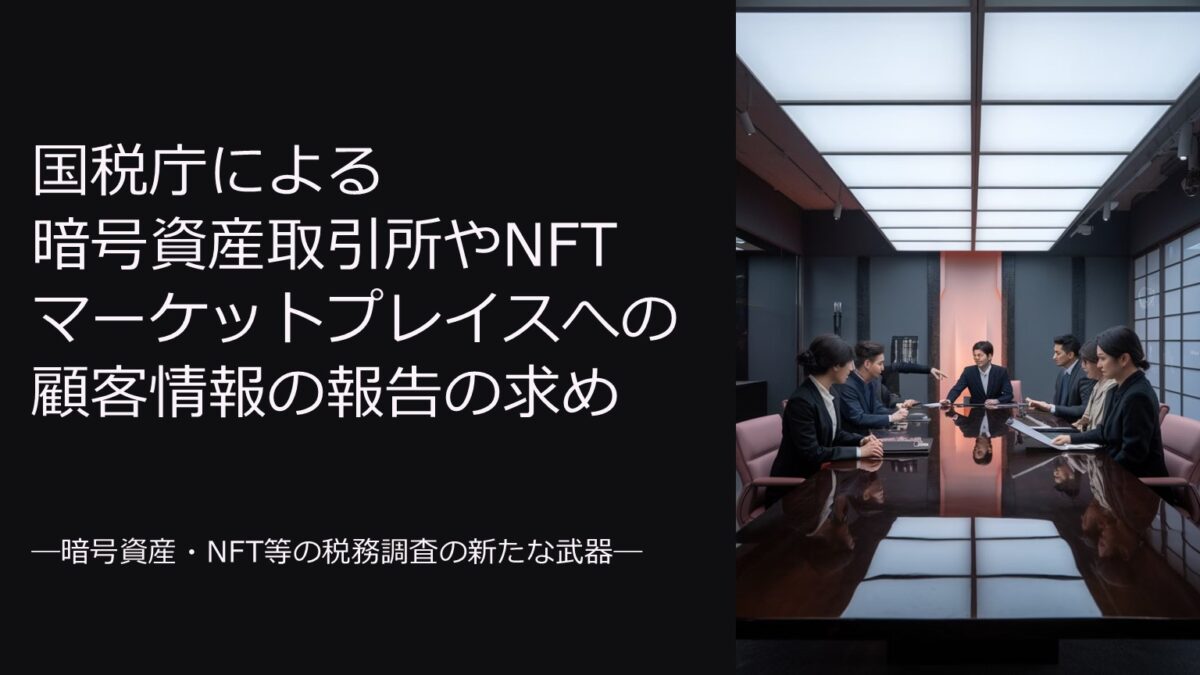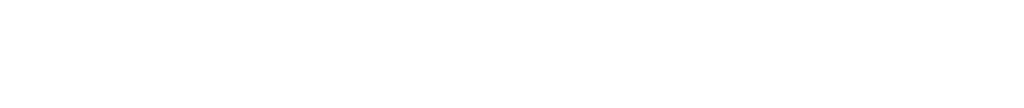本記事の紹介
近年、暗号資産(仮想通貨)やNFT取引に対する税務調査の強化 が進められています。特に、税務当局が無申告や申告漏れを把握しづらい暗号資産取引に対応するため、令和元年度税制改正により、「特定事業者等への報告の求め」 という新たな制度が導入されました。
本記事では、国税庁が暗号資産取引所やNFTマーケットプレイスに対し、顧客情報の報告を求める権限をどのように行使しているのか、その法的根拠や影響 について詳しく解説します。暗号資産の税務調査の最新動向を知り、適正な税務対応を行うためのポイントを整理しました。
▼この記事でわかること ✅
✅「特定事業者等への報告の求め」とは?(国税通則法74条の7の2の解説)
✅国税庁が暗号資産取引所・NFTマーケットプレイスに対して求める情報の範囲とは?
✅税務調査における「質問検査権」との違い
✅高額・悪質な無申告者への対応強化の具体的な施策
✅税務当局による取引情報の収集方法とその影響(取引額の一定基準以上の顧客データを要求)
暗号資産やNFT取引に関わるすべての個人・法人にとって、税務調査の最新動向を知ることは重要です。国税庁の新たな情報収集手法を理解し、適切な税務対策を講じるために、ぜひ本記事をご覧ください!
税務調査の質問検査権と事業者への報告の求め
税務調査において、税務職員が行使できる「質問検査権」という権限があります(国税通法74の2 ~74の6)。これは、国税に関する調査が必要な場合、税務職員が納税者に質問したり、帳簿や書類などを検査したり、その提示や提出を求めることができる権利です。この権限により、納税者は税務職員の質問に答える義務が生じ、帳簿書類などを提出しなければなりません。
もし、納税者が、正当な理由がないにもかかわらず、税務職員の質問に答えなかったり、虚偽の回答をしたり、検査や書類の提出を拒んだ場合、法に違反したことになり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります(国税通則法128二・三)。
高額・悪質な無申告者への対応強化
匿名で所得を得やすい暗号資産(仮想通貨)やインターネットを使った在宅ビジネスなどでは、誰がどれくらい収入を得ているのか把握しづらいため、税務調査の対象として特定しにくいという課題がありました。そこで、令和元(2019)年度の税制改正により、国税通則法74条の7の2 に「特定事業者等への報告の求め」という新たな仕組みが導入されました。
これは、特に悪質な無申告者などを特定し、適正な課税を行うために、事業者に対して高額な取引や収入に関する情報を報告するよう求めることができるものです。この報告の求めは、事業者が正当な理由がなく回答しない場合や虚偽の情報を提供した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるという罰則もあります(国税通則法74の7の2)
なお、同じタイミングで、事業者への協力要請に関する規定も法律に明記されましたが(国税通則法74の12①)、上記と異なり、調査の対象者の特定性や実効性確保の観点からの担保措置などに関する規定は定められていません。
さて、国税庁は、暗号資産やNFTの税務調査で使える「新しい武器」を手に入れたことになります。
具体的には、国税庁は、上記の「特定事業者等への報告の求め」を利用して、暗号資産取引所やNFTマーケットプレイス等の事業者に対して、「〇年〇月〇日~〇年〇月〇日の期間において、取引金額が■■■円以上の暗号資産取引を行っている個人顧客」の情報を報告させることができるのです。
これは、暗号資産取引所やNFTマーケットプレイス等の事業者に対して、「〇〇さんの取引情報を報告してください」などといったような特定の個人を指定して情報を求めることを前提としているものではありません。「取引金額が■■■円以上の暗号資産取引を行っている個人顧客」全員の情報の報告を求めることが可能なものです。
以下では、この「特定事業者等への報告の求め」の考え方、当該求めを行使できる要件、実際の手続、実際に使用している様式などについて、確認していきます。