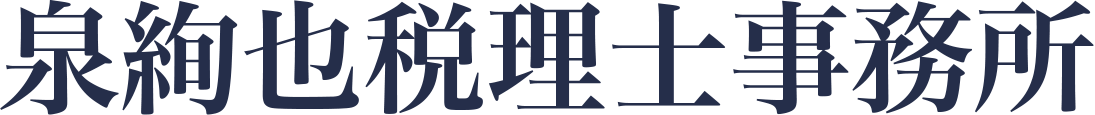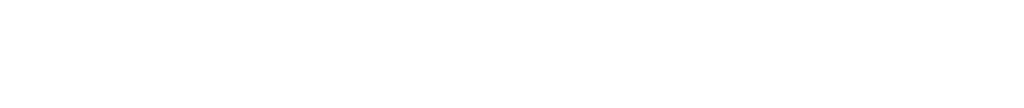記事の紹介
「早生まれは扶養控除で損をしている?」裁判所が出した結論とは
「同じ学年なのに、誕生日が1月〜3月の『早生まれ』の子だけ扶養控除が受けられない年があるのは不公平だ」――。そんな切実な訴えに対する判決が、令和6年1月12日、東京地方裁判所で言い渡されました。
●なぜ「差」が生まれるのか? 所得税の扶養控除は、その年の「12月31日時点」の年齢で判定されます。そのため、同じ高校1年生(15歳)でも、12月末までに16歳になる「遅生まれ」の子は控除対象になりますが、翌年1月以降に誕生日を迎える「早生まれ」の子は、その年の判定ではまだ15歳のため、控除が受けられないという現象が起こります。
●裁判所の判断:不平等ではないの? 原告の納税者は、この仕組みは「法の下の平等」を定めた憲法14条に反すると主張しました。しかし、裁判所は以下の理由から、国の仕組みは「合憲(憲法に違反しない)」と結論づけました。
- 所得再分配の目的: 現在の制度は「控除から手当へ」という方針に基づき、高所得者に有利な控除を減らす代わりに、低所得者に有利な「手当」へ移行するもので、その目的は正しい。
- 事務の効率性: 12月31日の現況で一律に判定することは、徴税のミスを防ぎ、効率的に税金を集めるために合理的である。
- 生涯で見れば同等: 浪人や留年、大学院進学などのケースも含めて考えれば、必ずしも早生まれだけが受給回数で損をするとは限らない。
結論として、「多少の差異が生じても、国の広い裁量の範囲内であり、著しく不合理とはいえない」とされました。家計に直結する切実な問題ですが、国会の立法裁量の広さや制度の「画一性」が優先された形です。
目次
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
請求
原告は、川崎北税務署長が令和3年12月24日付けで原告に対してした、次の各「更正をすべき理由がない旨の通知処分」の取消しを求めました。
- 平成29年分の所得税及び復興特別所得税に係る「更正をすべき理由がない旨の通知処分」
- 令和2年分の所得税及び復興特別所得税に係る「更正をすべき理由がない旨の通知処分」
事案の概要
本件は、原告が、所得税法2条1項34号の2 (令和2年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)に規定する控除対象扶養親族に「誕生日が1月2日から4月1日までの者(以下「早生まれ」又ほ「早生まれの者」といい、早生まれでない者を「遅生まれ」又は「遅生まれの者」という。)で15歳の者」が含まれていない部分及び同項34号の3に規定する特定扶養親族に「早生まれの者で18歳の者」が含まれていない部分(以下、併せて「早生まれ除外部分」という。)はいずれも憲法14条1項に反するから、
原告の早生まれの子は、
- 平成29年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)との関係で一般の控除対象扶養親族(控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族及び老人扶養親族を除いたものをいう。以下同じ。)に、
- 令和2年分の所得税等との関係で特定扶養親族に、それぞれ該当する旨主張し、
原告は、上記主張に基づいて、平成29年分及び令和2年分(以下「本件各年分」という。)の所得税等の各確定申告につき、それぞれ更正の請求をしました。
これに対して、川崎北税務署長は、それぞれ更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下、併せて「本件各通知処分」という。)を行ったため、原告はその取消しを求めました。
以下、本件訴えのうち、平成29年分の所得税等に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しの訴えを「本件平成29年分通知処分取消じの訴え」といいます。
前提事実
原告及びその子
原告は、本件各年分の所得税との関係において、給与所得者でした。
原告の三男である本件子は、原告と生計を一にしており、また合計所得金額は、所得税法2条1項34号の扶養親族に係る所得要件を満たしていました。
各確定申告
原告は、平成29年分の確定申告において、本件子を一般の控除対象扶養親族として申告しませんでした。
原告は、令和2年分の確定申告において、本件子を一般の控除対象扶養親族として申告しましたが、特定扶養親族としては申告しませんでした。
1回目の更正の請求等(別件)
原告は平成30年3月16日、寡夫控除の適用を求めて平成29年分につき更正の請求(別件更正の請求)をしました。
川崎北税務署長は平成30年4月25日付けで、これに対し更正をすべき理由がない旨の通知処分(別件通知処分)をしました。
原告は審査請求をしましたが棄却され、さらに別件訴訟を提起したものの、原告請求棄却の判決がされ、控訴審でも棄却判決がされ確定しました。
2回目の更正の請求等(本件)
原告は令和3年10月15日、扶養控除の適用に誤りがあるとして、本件各年分について更正の請求をしました。
川崎北税務署長は令和3年12月24日付けで、各年分について更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件各通知処分)をしました。
原告は審査請求をしましたが、一定期間までに裁決がされなかったため、令和4年5月10日、本件訴えを提起しました。
争点
本件平成29年分通知処分取消しの訴えの適法性(本案前の争点)
被告の主張
被告は、平成29年分については、別件訴訟と訴訟物が同一で既判力が及んでいること、また原告の主張は別件訴訟でも主張可能だったことを踏まえると、本件訴えは信義則に反し不適法である旨主張しました。
原告の主張
原告は、別件更正の請求では本件の主張をしていないため、別件訴訟で本件主張をすることはできず、主張のためには新たに更正の請求が必要であること、別件訴訟は本件と争点が異なり蒸し返しではないこと、さらに租税法律関係における信義則の適用は慎重であるべきこと等から、本件訴えは適法である旨主張しました。
本件各通知処分の適法性(本案の争点)
原告の主張
原告は、本件年齢規定に早生まれ除外部分があることで、早生まれの子を扶養する納税者が遅生まれの子を扶養する納税者より扶養控除で不利益を受けるとして、早生まれ除外部分は憲法14条1項に反し無効であり、本件子は平成29年分では一般の控除対象扶養親族、令和2年分では特定扶養親族に該当すると主張しました。また、平成22年改正の立法目的は「控除から手当へ」の観点で、子ども手当・就学支援金の対象との整合を図る趣旨であるべきで、早生まれ除外部分はその目的と合理的関連性がないとも主張しました。
【判決文より】
「本件年齢規定は、早生まれ除外部分があることにより、早生まれの子について、ある年の1月1日から3月31日までの間に15歳又は1 8歳に達した場合、その年の12月31日の時点で子ども手当又は就学支援金の支給対象外であるにもかかわらず、そのような者について一般の控除対象扶養親族又は特定扶養親族に該当しないこととなるから、前記アの立法目的との間で合理的関連性がない。」
被告の主張
被告は、平成22年改正の立法目的は、扶養控除の担税力調整の趣旨を維持しつつ、「控除から手当へ」を進め、低所得者に相対的に有利な支援を行い、所得税の再分配機能の回復を図る点にあるとし、個別の納税者ごとに児童手当等との一致を求める趣旨ではないと主張しました。また、控除対象扶養親族・特定扶養親族の判定は所得税法85条3項により12月31日の現況で画一的に行われ、そこに一定の差異が生じ得るとしても、徴税の便宜や暦年課税との整合性の観点から不合理ではないとして、本件各通知処分は適法と主張しました。
裁判所の判断
本件平成29年分通知処分取消しの訴えの適法性
裁判所は、国税通則法23条1項1号は、更正の請求について法定申告期限から5年以内という制限を置く一方で、回数の制限を設けていないこと、また「更正すべき理由として主張できる事由は必ず全て主張しなければならない」といった義務付けが当然に導かれるものではないことを踏まえ、複数回の更正の請求と、それに対応する各通知処分ごとの取消訴訟提起自体は妨げられないとしました。
そして、原告は別件と異なる事由に基づいて適法に更正の請求をし、その上で本件訴えを提起したのであり、別件訴訟の不当な蒸し返しと認め難く、濫用的提起を認める証拠もないとして、信義則違反は否定し、本件平成29年分通知処分取消しの訴えは適法と判断しました。
本件各通知処分の適法性(憲法14条1項違反の有無)
判断枠組み
裁判所は、憲法14条1項は絶対的平等を保障するものではなく、合理性のある区別は許されること、さらに租税法分野は財政・経済・社会政策等の総合判断や専門技術的判断を伴うため、立法府の裁量が広く、裁判所はこれを尊重すべきであるとしました。その上で、租税法上の区別は、立法目的が正当で、かつ採用された区別の態様が目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項違反とはいえないという枠組みを示しました。
平成22年改正の立法目的
裁判所は、扶養控除などの所得控除は限界税率に応じて減税効果が変わるため、累進税率の下では高所得者に相対的に有利になり得る点を整理した上で、平成22年度税制改正大綱等に照らし、平成22年改正の目的は、高所得者に有利な面のある所得控除から手当(又は税額控除)へ移行する「控除から手当へ」を進め、低所得者に相対的に有利な支援を行い、所得税の再分配機能の回復等を図る点にあるとし、これは正当であると判断しました。原告のいう「児童手当・就学支援金の対象と扶養控除廃止を個別に対応させる」理解については、そこまでを目的とするものではないとして採用しませんでした。
早生まれ除外部分が「著しく不合理」といえるか
裁判所は、平成22年改正により18歳以下の子を扶養する世帯で扶養控除の一部廃止に伴う不利益が生じ得る一方で、児童手当や就学支援金制度の導入による定額給付拡充の恩恵も受け得ることから、本件年齢規定は所得再分配機能の向上に資する面があり、立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかとはいえないとしました。
また、原告が指摘する「同一学年で早生まれと遅生まれにより、高校1年・大学1年の局面で差が出る」といった点についても、裁判所は、浪人・留年・大学院進学等のケースを含めて見れば、文言上、該当回数に差異を設けているものではないこと、原告がいう不利益は、基準日(12月31日)において一定額以上の収入があること等により生じる面もあること、そして所得税法は暦年課税であり、所得税法85条3項が12月31日現況による一律判定を採用していることは徴税の便宜にも資し、暦年単位の計算とも整合するとして、暦年基準で画一的に定めたことが立法目的との関連で著しく不合理とまでは認められないとしました。
以上から、裁判所は、本件年齢規定のうち早生まれ除外部分は憲法14条1項に反しないとし、本件子が一般の控除対象扶養親族・特定扶養親族に該当しないものとしてされた本件各通知処分は、いずれも適法であると判断しました。
【判決文より】
「(2)平成22年改正の経緯等(乙8)
扶養控除は、自己と生計を一にする一定の所得金額以下の親族(扶養親族)を有する場合に、その人数等に応じて納税者の担税力調整を行う趣旨で設けられているが、この扶養控除などの所得控除制度は、課税対象となる所得から一定額を差し引くものであり、この制度による税負担軽減額は、基本的には、この一定額に各々の納税者に適用されている限界税率を乗じた額となる。
したがって、累進税率を採用している所得税においては、高所得者に適用される限界税率が高いことから、所得控除制度による高所得者の負担軽減額は相対的に大きくなる一方で、低い税率の適用される低所得者の負担軽減は相対的に小さくなる。
平成22年度税制改正大綱においては、このように高所得者に有利な面がある所得控除について、ー律の税額控除に変えれば、限界税率の低い低所得者ほど所得比で見た負担軽減効果が大きな仕組みになり、あるいは、手当に変えれば、定額の給付であることから相対的に支援の必要な人に実質的に有利な支援を行うことができるとされ、所得税改革の方向性の一つとして、所得税の所得再分配機能の回復等の観点から、所得控除から税額控除や手当等への転換を進めること(「控除から手当へ」)が挙げられた。
平成22年改正においては、こうした所得税改革の方向性を踏まえ、支え合う社会づくりの第一歩として、子どもの養育を社会全体で支援するとの観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されるとともに、公立高等学校の授業料の無償化等に伴い、16歳以上・1 9歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止された。
(3)平成22年改正の立法目的について
ア 前記(2)のとおり、平成22年改正の立法目的は、高所得者に有利な面のある所得控除から、手当(又は税額控除)への移行(「控除から手当へ」)を進め、支援の必要性が相対的に大きい低所得者につき、実質的に有利な支援を行い、所得税の所得再分配機能の回復等を図ることにあるといえ、この立法目的は、正当である。
イ これに対し、原告は、平成22年改正の立法目的は、子ども手当の支給対象である扶養親族に対する扶養控除を廃止し、就学支援金の支給対象である扶養親族に対する扶養控除額の上乗せ部分を廃止することにあり、このように解しなければ、平成22年改正の立法目的は人的事情に基づく担税力の調整という扶養控除の趣旨に適合せず、正当性を欠く旨主張する。
しかし、平成22年改正の立法目的は、前記アのとおりであって、それ以上に、個別の納税者に対し、扶養控除又は扶養控除額の上乗せ部分の廃止と引き換えに、子ども手当又は就学支援金を支給することまで目的とするものではない。そして、人的事情に基づく担税力の調整という扶養控除の趣旨に照らしても、前記(2)のような、「控除から手当へ」という、子ども手当制度や就学支援金制度の創設を伴う所得税改革の方向性を踏まえれば、かかる解釈が扶養控除の趣旨に適合しなくなるものではない。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(4) 本件年齢規定のうち早生まれ除外部分が平成22年改正の立法目的との関連で著しく不合理であることが朋らかといえるかについて
ア 平成22年改正により、本件年齢規定に基づき扶養控除がされるようになったことで、18歳以下の子を扶養する子育て世帯において、扶養控除の一部廃止に伴う不利益が生じることとなったが、その不利益は、低所得者が高所得者に比して小さく(前記(2))、一方で、上記世帯において、子
ども手当や就学支援金制度による定額給付拡充の恩恵を受けられることとなったから、本件年齢規定は、所得税の所得再分配機能の向上に資するものといえ、前記(3)の平成22年改正の立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかであるとはいえない。
これに対し、原告は、本件年齢規定のうち早生まれ除外部分について、早生まれの子につき、子ども手当や就学支援金の支給対象外にもかかわらず、一般の控除対象扶養親族や特定扶養親族に該当しない場合があることは、上記立法目的との間で合理的関連性がない旨主張する。
しかし、前記(3)イのとおり、平成22年改正は、個別の納税者に対し、扶養控除又は扶養控除額の―上乗せ部分の廃止と引き換えに、子ども手当又は就学支援金を支給することまで目的とするものではないまた、本件年齢規定の文言上、扶養親族が一般の控除対象扶養親族及び特定扶養親族に該当し得る回数につき、同一学年の早生まれの者と遅生まれの者との間で差異を設けているものではない。すなわち、例えば、早生まれの者が高等・学校卒業後、大学受験のために浪人をした場合や大学で留年した場合、大学卒業後、大学院に進学するなどしてすぐに就職せず、一定額以上の収入を得なかった場合などであれば、その者と同一学年の遅生まれの者が高校卒業後すぐに大学に進学し、留年せずに大学を卒業した後すぐに就職して一定額以上の収入を得た場合と、特定扶養親族に該当する回数は同じになるのであり、こうして見ると、原告が主張する早生まれの子を扶養する納税者の不利益は、所得税法85粂3項の規定する基準日においてその扶養する子に一定額以上の収入かあることが理由となって生じるものにすぎないといえ、かかる不利益は、人的事情に基づく担税力の調整という扶養控除の趣旨から当然に予定されているものといえる。
そして、所得税法においては、暦年を課税年度とし、課税標準の計算も暦年単位で行っていること、同法85条3項は、一般の控除対象扶養親族又は特定扶養親族に該当するかどうかの判定をその年の12月31日の現況により一律的に行う旨を定めており、これが特段不合理とはいえないことからすれば、本件年齢規定について、徴税の便宜や所得税法の各規定との整合性の観点から、暦年を基準として規定したことが、平成22年改正の立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかとまでは認められない(なお、原告は、本件年齢規定に早生まれの者を含めなかったとしても徴税コストは抑制されるわけではない、本件年齢規定に早生まれの者を含めても所得税法8 5条8項との整合性は維持できるなどとも主張するが、所得税法における諸規定を暦年に基づいて規定することは、過誤の減少等につながり、徴税の便宜に資するし、本件年齢規定に早生まれの者を含めるこどによって所得税法85条3項が暦年を基準として規定されていることと整合しなくなるのは明らかであるから、原告の上記主張は理由がない。)。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。
そのほか、原告は、本件年齢規定のうち早生まれ除外部分の合理性につき;扶養親族が19歳未満である間に平成22年改正が施行された場合、当該扶養親族が早生まれのときは、遅生まれのときと比較して、当該扶養親族が一般の控除対象扶養親族又は特定扶養親族に該当する回数が1回少なくなるとか、本件年齢規定のうち早生まれ除外部分は独立行政法人日本学生支援機構による給付奨学金の家計基準の審査にも影響を及ぼしているなどとも主張するが、かかる主張により、当裁判所の上記判断が左右されるものではない。」
結論
裁判所は、
- 平成29年分の訴えは適法とした上で、
- 本案については、早生まれ除外部分は憲法14条1項に反しないとして、
原告の請求はいずれも理由がないとして棄却し、主文のとおり判断しました。
控訴審(東京高裁令和6年5月23日判決)の判断
控訴審である東京高裁令和6年5月23日判決も、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却する、とされました。
【判決文より】
「控訴人は、平成22年改正の立法目的は、扶養控除から子ども手当への切替えを実現するための所得税法側の措置として、子ども手当の支給要件児童とみなされる年齢の扶養親族を控除対象外とするように講じることと、特定扶養控除から就学支援金への切替えを実現するための所得税法側の措置として、就学支援金の支給対象とみなされる年齢の扶養親族を控除対象外とするように講じることである旨主張する。
しかし、平成22年改正の立法目的は、高所得者に有利な面のある所得控除から、手当(又は税額控除)への移行(「控除から手当へ」)を進め、支援の必要性が相対的に大きい低所得者にっき、実質的に有利な支援を行い、所得税の所得再分配機能の回復等を図ることにあるのであって、それ以上に、個別の納税者に対し、扶養控除又は扶養控除額の上乗せ部分の廃止と引き換えに、子ども手当又は就学支援金を支給すること(扶養控除又は特定扶養控除から子ども手当又は就学支援金への切替え)まで目的とするものではない(引用に係る原判決「事実及び理由」(補正後のもの。以下「原判決」という。)第3の2(3))。
したがって、控訴人の上記主張は採用できない。
(2) 控訴人は、同年に出生9した早生まれの子を扶養する納税者は遅生まれの子を扶養する納税者と比較して扶養控除又は特定扶養控除の適用開始が遅れる不利益を被るところ、本件年齢規定は、その代替となる給付もなく扶養控除又は特定扶養控除を廃止したものであるから、仮に平成22年改正の立法目的を原判決のように解したとしても、立法目的との間に合理的関連性がなく、憲法14条1項に違反する旨主張する。
しかし、前記(1)のとおり、平成22年改正は、個別の納税者に対し、扶養控除又は扶養控除額の上乗せ部分の廃止と引き換えに、子ども手当又は就学支援金を支給すること(扶養控除又は特定扶養控除から子ども手当又は就学支援金への切替え)まで目的とするものではない。
また、控訴人が主張する早生まれの子を扶養する納税者の不利益は、結局のところ、子ども手当等の支給要件については「15 歳に達する日以後の最初の3 月3 1日までの間」と定められているのに対し、所得税法(暦年を課税年度とし、課税標準の計算も暦年単位で行っている。)が、一般の控除対象扶養親族又は特定扶養親族に該当するかの判定を「その年12月31日の現況」により一律的に行う旨規定したこと(同法85条3項)に起因するものであるところ、本件年齢規定について、徴税の便宜や所得税法の各規定の整合性の観点から、暦年を基準として規定したこどは、立法府の政策的、技術的な裁量的判断であって、基本的に尊重せざるを得ないものであり、控訴人主張の諸点を考慮しても、平成22年改正の立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかとまでは認められない(原判決第3の2(4)) 。
したがって、控訴人の上記主張は採用できない。」