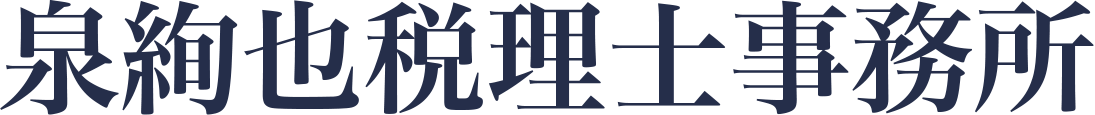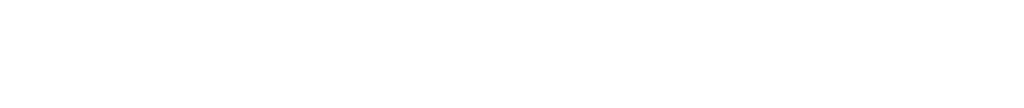本件は、原告会社が、太陽光発電事業に用いる土地(本件土地②)について、B社との間で地上権設定契約(B契約)を締結し、権利金5億円(本件権利金)を受け取る合意をしたにもかかわらず、これを収益計上せず法人税等の申告をしたとして、廿日市税務署長から更正処分および重加算税賦課決定処分を受けた事案である。原告は、①B契約はC社に圧力をかけるための外観作出にすぎず、通謀虚偽表示により無効である、②仮に有効でも土地の引渡し等がされていないから本件事業年度に収益は確定していない、③重加算税の前提となる隠ぺい・仮装はない、と主張した。
広島地判令和5年7月31日税資273号順号13869は、B契約書には地代免除禁止、原状回復、遅延損害金等、単なる外観作出目的なら不要な条項が多数あり、敷金を返還不要の「権利金」に変更した体裁も含めて、実体のある地上権設定契約とみるのが自然であるとした。さらに、B社が登記費用を負担して地上権設定登記を具備したこと、同額5億円が後日支払われたこと(裁判所は本件権利金の支払と評価)などから、通謀虚偽表示による無効は否定した。
収益計上時期については、収益は「収入すべき権利が確定した時」に計上すべきであり、地上権は設定行為により成立し、遅くとも地上権設定登記がされた時点で対価たる権利金支払請求権は確定すると判断した。土地の引渡しを要するとの原告主張も、地上権設定の対価が権利金、使用の対価が地代という通常理解から採用しなかった。
「(2)争点2(本件権利金の収益としての計上時期)について
ア 前記第2の2(1)のとおり、法人税法22条2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引に係る収益の額とするものとし、同条4項は、当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算すべきものとしている。したがって、ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の収益に計上すべきである(最高裁平成5年11月25日第一小法廷判決・民集47巻9号5278頁参照)。
イ B契約は、原告がB社のために太陽光発電設備を所有するための利用権である地上権を本件土地②に設定し、B社が、その対価として本件権利金を支払うこととするものであり、地上権設定登記手続の実施を想定して同登記に要する費用をB社が負担する旨を定めていることは前記認定事実のとおりである。地上権は設定行為により成立する(民法176条)ところ、B社のための地上権設定の効果はB契約締結時に生じており、地上権設定登記は平成29年7月18日に具備されているため、遅くとも同日の時点で、地上権設定の対価としての本件権利金の支払請求権は権利として確定したとみるのが相当であるから、本件権利金を本件事業年度の収益として計上することが一般に公正妥当と認められる会計処理というべきである。
原告は、B契約書上、B社は本件土地②を太陽光発電設備を所有する目的のために使用すると定められている以上、使用できる状態とすること、すなわち本件土地②の引渡しも原告の債務であると解するべきであるところ、本件事業年度においてB社に対する本件土地②の引渡しは履行されていないため、本件権利金に係る権利は確定しておらず、したがって、これを本件事業年度の収益として計上することはできない旨主張する。しかしながら、一般的には、地上権の設定の対価が権利金であり、使用できる状態とすること、すなわち引渡しの対価が地代であると解され、B契約が特段これと異なる解釈をすべき事情はうかがわれないから、地代について別途定められているB契約において、地上権の設定のみならず本件土地②を引渡しまでなされないと対価である本
重加算税については、甲が顧問税理士にB契約の存在を秘匿し、調査でも金銭の性質を敷金等と説明していたこと、本件確認書への署名押印などから、当初から過少申告を意図し外形的行動を伴う隠ぺい・仮装があるとして賦課要件充足を認め、原告請求を棄却した。
「ア 重加算税の制度は、納税者が過少申告をするについて、隠ぺい又は仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を科すことによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするものであるから、国税通則法68条1項にいう隠ぺい又は仮装があるというためには、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい又は仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するが、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要なわけではなく、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の賦課要件が満たされるものと解すべきである(最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決・民集49巻4号1193頁)。
イ B契約書には本件権利金は返還しない旨が条文で明記されているが、前記1の認定事実によれば、同条文は甲の指示により丁司法書士が入れた条文であることが認められるから、甲は本件権利金を返還しなくてよいことを明らかにするために同条文を入れるよう丁司法書士に指示したもの、すなわち返還を要しない金銭であることを認識していたものといえる。また、地上権の設定の対価である本件権利金に係る権利が、地上権設定合意がなされて地上権設定登記が具備されたことで平成29年7月18日には確定的なものとなったこと(前記3(2)イ)は、遅くとも平成10年9月20日以降は不動産業を営んでおり(前記第2の3(1))、また、収益として計上すべき収入か否かを判断する程度には税務の知識を有していたと認められる(前記1(3)ア参照)甲であれば、優に認識していたものといえる。そうすると、甲は、地上権設定登記が具備された日の属する本件事業年度の収益に本件権利金を計上すべきであることを熟知していたということができる。
また、前記1の認定事実及び上記「甲は本件事業年度の収益に本件権利金を計上すべきことを熟知していた」との評価によれば、甲は、本件事業年度の原告の税務申告の手続を行おうと収益として計上する収入の有無を問うた丙税理士に対し、本件権利金に関する確定的な脱税の意思に基づいて、本件権利金の存在を秘匿し、B合意の存在を報告することもB合意書を提示することもなく、丙税理士に過少な申告を記載した納税申告書を作成させ、これを被告に提出したということができる。そもそも、本件事業年度における原告の純売上は162万円である(乙37・7枚目)にもかかわらず、地代が1年分1億5000万円、20年分の合計で30億円、権利金が5億円とされるB合意に関して、原告の税務申告を担当する顧問税理士に対して何ら報告していないということ自体、甲の秘匿の意思が強く推認されるところである。
なお、前記1の認定事実によれば、甲は、丙税理士から、本件確認書に署名押印すれば本件権利金の隠ぺい又は仮装をしたことを認めることになる旨の説明を受けた上で、「本件権利金が収益として確定していたにも関わらず、丙税理士にも本件権利金の存在を報告しないことでの納税申告書に本件権利金を収益として反映させず、課税を免れたことを確認する」旨記載された本件確認書に署名押印しているのである。原告は、本件確認書には事実と異なることが記載されていたが、本件調査を終わらせたいとの思いから、あるいは「内容は事実と異なるが、和解である」と説明されたことから、署名押印したと主張し、甲もその旨供述するが、隠ぺい又は仮装という強固な脱税の意思を有していたことを認めることになる旨の説明を受けてもなお署名押印をする理由としてはあまりに不自然であるから、上記の原告の主張は採用しない。
以上によれば、原告(甲)は、当初から本件権利金を収益として計上しないことによって過少な申告をすることを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものということができるから、その意図に基づいて原告のした本件の過少申告行為は、国税通則法68条1項所定の重加算税の賦課要件を満たすものというべきである。」
ダウンロード資料