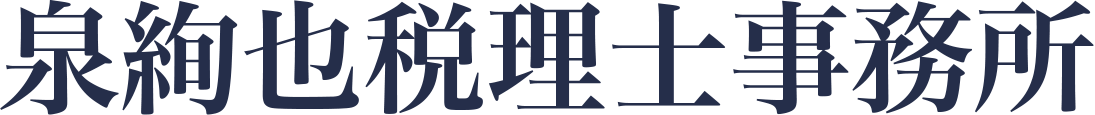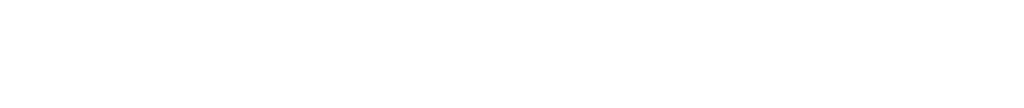早期退職制度(希望退職)に応募した際、上乗せされる「特別加算金」。老後の資金として期待していたのに、想定外に重い税金が源泉徴収されていたら……。
今回ご紹介する福岡地裁令和6年7月18日判決は、まさにそんな事態に直面した元執行役員が、会社を相手取って損害賠償を求めた事案です。争点は、令和3年度の税制改正で導入された「短期退職手当等」の規定。勤続5年以下の所得に対し、退職金の税制メリットである「2分の1課税」を制限する仕組みです。
原告は「子会社時代を含めれば勤続10年以上であり、短期退職には当たらない」と主張しましたが、裁判所は厳しい判断を下しました。M&Aやグループ内転籍、キャリアアップを重ねるビジネスパーソンにとって、他人事ではないでしょう。要注意です。
事案の概要
本件は、子会社を退職して親会社に入社した後、希望退職募集に応募して早期退職した原告が、早期退職特別加算金について、被告がこれを所得税法上の「短期退職手当等」に該当するとして源泉徴収を行ったことが、所得税法の適用を誤った違法な源泉徴収であり、不法行為に当たると主張し、本来適用されるべき「一般退職手当等」としての源泉徴収額との差額の損害賠償を求めた事案である。
原告は、当該特別加算金は早期退職を促すための割増退職金であり、短期勤続を前提とする制度趣旨とは異なると主張したのに対し、被告は、勤続年数が5年以下であることを理由に短期退職手当等に該当するとして争った。
なお、国が補助参加している。
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
請求
原告は、被告に対し、早期退職特別加算金について過大に源泉徴収された金額相当額及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。
前提事実
当事者の地位等
被告は、通信機器・装置・システムの製造・販売等を目的とする株式会社である。
原告は、被告の子会社に中途入社し、同社において執行役員を務めた後、当該子会社が被告に吸収合併されたことに伴い、被告に入社した。
子会社からの退職金等の支払
原告は、平成10年7月に子会社に中途入社し、平成30年4月に同社の執行役員に就任した後、本件子会社が被告に吸収合併されたことに伴い、令和3年3月31日に本件子会社の執行役員を退任し、翌4月1日に被告に入社した。
原告は、平成30年4月、子会社の執行役員に就任するに当たり、従業員を退職することに伴う退職金を受領し、令和3年4月、子会社の執行役員を退任するに当たり、役員退職慰労金を受領した。
早期退職募集と特別加算金の支払
被告は、一定の年齢・地位にある者を対象として、通常の退職金に加えて特別加算金を支給する早期退職者募集を行った。
原告はこれに応募し、所定の退職日に退職した。
被告は、原告に対し、通常の退職金に加えて早期退職特別加算金を支給したが、当該特別加算金について、短期退職手当等に該当するとして源泉徴収を行った。
争点
本件の争点は、次の2点である。
争点1
早期退職特別加算金を一般退職手当等ではなく、短期退職手当等に該当するとして被告が行った源泉徴収が、所得税法の適用を誤ったものか否か
争点2
被告に故意又は過失が認められるか否か
争点に関する当事者の主張
被告及び補助参加人の主張(争点1)
短期退職手当等に該当するためには、
退職により一時に受ける給与であること、
短期勤続年数に対応する退職手当等として支払われたこと、
所得税法30条5項所定の特定役員退職手当等に該当しないこと
の各要件を満たす必要がある。
本件特別加算金は、退職により一時に受ける給与であり、特定役員退職手当等にも該当せず、また、勤続年数は被告に入社してから退職までの1年間に限られるから、短期退職手当等に該当すると主張する。
原告の主張(争点1)
原告は、勤続年数の算定に当たっては、子会社での勤務期間も通算すべきであり、本件特別加算金は一般退職手当等に該当すると主張する。
また、短期退職手当等の制度は、短期間のみ在籍することが当初から予定されている者による租税回避を防止する趣旨であり、早期退職募集に応じた割増退職金を想定したものではないから、本件特別加算金を短期退職手当等とするのは法の趣旨に反する拡大解釈であると主張する。
原告の主張(争点2)
被告は、特別加算金の性質について慎重な検討をせず、税務当局への事前確認も行わなかったとして、源泉徴収義務者としての注意義務を怠ったと主張する。
被告の主張(争点2)
仮に課税関係に争いがあったとしても、被告は法令の文言に従って源泉徴収を行っており、後に税務署からもその取扱いを追認する回答を得ていることから、故意又は過失は認められないと主張する。
裁判所の判断
争点1:本件特別加算金を一般退職手当等(所得税法30条7項)ではなく短期退職手当等(同法30条4項)に該当するとして被告の行った源泉徴収が、所得税法の適用を誤ったものであるか否か
裁判所は、短期退職手当等に該当するか否かは、退職手当等がいかなる勤続年数に対応して支払われたものであるかによって判断すべきであるとした。
本件では、原告は、子会社における従業員期間及び役員期間に対応する退職金等を既に受領しており、それらの期間は勤続年数に含めることができないとした。
また、本件特別加算金は、勤続年数に応じて計算されるものではなく、退職時の年齢や月収を基礎として算定されていることから、勤続10年以上という応募要件が設けられていたとしても、それが勤続年数の通算を意味するものではないとした。
その結果、原告の勤続年数は被告入社後の1年間に限られ、5年以下である以上、本件特別加算金は短期退職手当等に該当すると判断した。
さらに、短期退職手当等の制度趣旨との関係についても、原告が既に子会社において十分な退職所得控除を受けていることなどを踏まえれば、本件特別加算金を短期退職手当等とすることが公平負担の原則に反するとはいえないとした。
「本件早期退職者募集が勤続10年以上の者を対象としていることからすれば、被告は、原告が本件子会の従業員及び役員として勤務した期間を含めて被告における勤続年数を把握しているようであり(弁論の全趣旨)、本件子会社において勤務した期間を含めて所得税法施行令69条1項1号にいう「退職の日まで引き続き勤務した期間」とみる余地があるが、前提事実(2)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、①平成30年4月に本件子会社の執行役員に就任するに当たり、従業員を退職することに伴う退職金について、本件子会社の従業員であった期間を基に本件子会社から支払を受け、②令和3年4月に本件子会社の執行役員を退任するに当たり、役員退職慰労金について、本件子会社の執行役員であった期間を基に同社を吸収合併した被告から支払を受けていることが認められるから、同号ハ本文により、これら退職手当等(退職金及び役員退職慰労金)の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日(令和3年3月31日)以前の期間は勤続年数に含まれないものと解される。」
「また、同号ハただし書について、本件早期退職者募集の募集要項(前提事実(3)ア)及び被告と税務署とのやり取り(乙3、4) をみても、勤続10年以上という応募要件を満たした後は、具体的な勤続期間にかかわらず退職時の月収や退職時年齢別の加算月数(早期退職を促すべく加算月数は56歳が
最多となっている。)によって計算されるものであり、本件子会社の吸収合併によって被告に雇用される前の勤務期間を含めて計算されているものではないから、本件特別加算金について、同ただし書の適用はないものというべきである。
したがって、原告の勤続年数は、同人が被告に入社した令和3年4月1日から退職する令和4年3月31日までの1年間であり、勤続年数は5年以下であって、本件特別加算金は短期退職手当等に該当するものと認められる。」
「原告は、短期退職金手当等の制度を設けた令和3年度税制改正の趣旨は早期割増退職金には妥当せず、本件特別加算金を短期退職手当等とすることは法の趣旨に反する拡大解釈であると主張する。
租税法の基本理念は、租税法律主義及び公平負担の原則であり、これをいかに調和させるかが求められるところ(甲4参照)、前記(2)で判断したとおり、本件特別加算金を短期退職手当等に該当するものと解することは、所得税法30条4項、同法施行令69条1項1号の文言解釈に合致するものである上、原告は本件子会社において勤務していた期間に対応する退職金及び役員退職慰労金については、本件早期退職者募集とは無関係に受領して適正な退職所得控除を受けているものと解され、本件早期退職者募集に応募したことによって結果的に被告における勤続年数が5年以下となったのは原告の選択によるものであって、公平負担の原則に反するものともいえない。したがって、本件特別加算金を短期退職手当等とすることが法の趣旨に反するものとは認められない。
かえって、証拠(甲3) によれば、退職手当等は一般的に過去からの長期間にわたる勤労の対価の後払いという性格を持つと、ともに退職後の生活の原資に充てられるという特性を有しており、その担税力は他の所得に比べて低いため、累進税率の適用を緩和して税負担の平準化を図る観点から、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を課税対象とする措置(以下「2分の1課税」という。)が講じられているところ、令和3年度税制改正においては、現下の退職給付の実態をみると、法人の役員等以外についても勤続年数5年以下の短期間で支払われる退職金について、平準化の趣旨にそぐわない、特に高額な支給実態もみられることに基づいている。そうすると、本件早期退職者募集において、前提事実(2)のとおり、原告は本件子会社において従業員としての退職金及び執行役員としての退職金を受領しているから、更に被告において本件特別加算金を含む退職金を受領して2分の1課税の適用を受けることは、当初から被告においてI0年以上にわたって勤務して初めて特別加算金を含む退職金を受領する従業員との関係で、税負担の標準化を図る趣旨に反するものであるから、原告が受領する本件特別加算金を短期退職手当等と扱うことは、令和3年度税制改正の趣旨にも沿うものといえる。」
争点2:被告の故意又は過失の有無
裁判所は、被告に故意又は過失は認められないと判断した。
「本件特別加算金が短期退職手当等(所得税法30条4項)に該当しないことは前記で判断したとおりであるが、仮にこれに該当すると事後的に判断されたとしても、被告による本件特別加算金に係る源泉徴収は、所得税法30条や同法施行令69条の文言に忠実に従ってなされたものであり、上記源泉徴収後の令和4年7月に被告が税務署に対して行った照会に対して、同税務署が被告による源泉徴収の方法を追認する回答をしていること・・・からすれば、当時の税務当局の見解も被告の認識と一致していたものと認められるから、被告において、同年5月に行った源泉徴収の当時、本件特別加算金が短期退職手当等(同法30条4項)に該当するとの運用が違法であると認識することができたとは認められず、被告に故意又は過失は認められない。」
結論
以上のとおり、被告が早期退職特別加算金を短期退職手当等として源泉徴収したことは、所得税法の適用を誤ったものとはいえず、不法行為にも該当しないとして、原告の請求はいずれも棄却された。