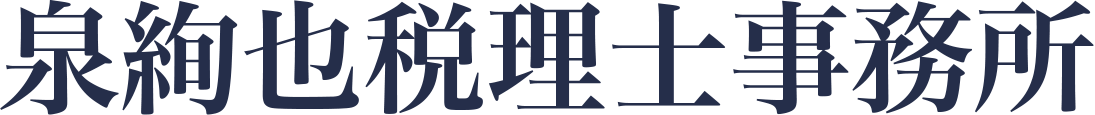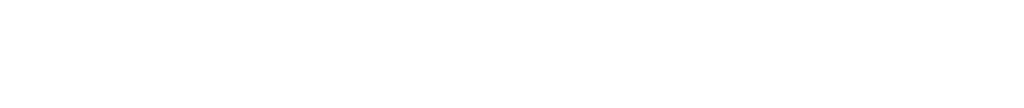土地を売った時、借地権の分を「値引き」して申告できる?最新判決の教訓
はじめに:何が争われたのか?
建物所有目的で他人の土地(底地)を借りる場合、その土地の借主には借地権が成立します。今回ご紹介するのは、土地を所有する「個人」と、その土地を借りて建物を建てていた「会社」が、土地と建物をまとめて第三者に約55億円で売却した際のお話です。
各土地が所在する地区は、借地権割合が90パーセントとされる商業地区でした。
この土地オーナー(原告)は、「土地代金のうち20%分は、建物を建てていた会社の『借地権』の対価だから、自分の収入ではない」として税金を計算し、申告しました。しかし、税務署は「いや、借地権の価値はゼロのはず。土地代の全額があなたの収入です」と更正処分(税金の増額)を行いました。これを不服としたオーナーが、処分の取り消しを求めて裁判を起こしたのです。
鍵を握る「無償返還届出書」
なぜ税務署は「借地権はゼロ」と言い出したのでしょうか。それは、オーナーと会社が以前、税務署に「無償返還届出書」という書類を出していたからです。
これは通常、「将来、土地を返す時はタダで返します(借地権の主張はしません)」という約束を税務署に伝える書類です。これを出しておくことで、会社側が「借地権をもらった」とみなされて高い税金(受贈益)を課されるのを防ぐことができます。
裁判所の判断:書類を出した以上、価値はオーナーにある
裁判所は、次のような理由でオーナー側の訴えを退け、税務署の主張を全面的に認めました 。
- 経済的価値の帰属: 無償返還届出書を出しているということは、「借地権の経済的価値は会社に移っておらず、オーナー(地主)に残っている」という事実を、自ら税務署に明らかにしたということである 。
- 売買代金の中身: 買い手との契約書でも土地代の全額が記載されており、その中には当然、オーナーの元に残っていた借地権相当の価値も含まれていると判断された 。
- 独自の合意は無効: オーナーと会社の間で「土地代の20%を会社に分ける」という独自の合意があっても、それは身内での分配案に過ぎず、税務上の「資産の増加益」の計算を左右するものではない 。
まとめ:税務書類の重みを再認識しよう
今回の判決(大阪地判令和7年1月17日)は、たとえ不動産売却時に当事者間で「借地権に価値がある」と合意していても、過去に出した税務上の届出書の内容(無償返還の約束)が優先されました 。
不動産の共同売却や親族間・同族会社間での取引を行う際は、過去の届出状況を確認し、税務上の実態と矛盾がないか慎重に検討する必要があります。専門家との相談がいかに重要かを物語る判決と言えるでしょう。
「争点1 (原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の計算において、総収入金額に本件各土地に係る借地権価額相当額を算入すべきか否か。)
(1}譲渡所得の判断枠組み等
ア 所得税法33条1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨規定し、同条3項は、譲渡所得の金額は、その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする旨規定している。
そして、譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものと解すべきであり、売買交換等によりその資産の移転が対価の移転を伴うときは、右増加益が対価のうちに具体化されるので、法はこれを課税の対象として捉えたものと解すべきである (最高裁昭和 43年10月31日第一小法廷判決・集民 92号797 頁、最高裁昭和 47年 12月26日第三小法廷判決・民集26巻10号20 83頁参照)。
そうすると、複数の者がそれぞれの有する資産を第三者に一括して有償で売却した場合における各資産の所有者に係る譲渡所得の総収入金額は、当該売買の対価のうちに占めるそれぞれの資産の所有者に帰属すべき資産の増加益が具体化された金額により計算されるものと解すべきであるから、本件売買契約における原告の譲渡所得の総収入金額は、本件売買契約の売買代金(対価)のうちの原告の所有する本件各土地という資産の増加益が具体化された金額によることになる。」
「(2) 借地権に係る課税上の取扱い
ア 地主が法人である場合
(ア) 原則的な場合
借地権の設定は、借地借家法により借地人の地位に強い保護が与えられている結果、経済的、実質的には所有権の権能の一部を譲渡するという側面があるから、借地権を設定する際、地主から借地人に対し借地権部分に相当する経滋的価値の移転があったと見るべき経済実態が存在する場合には、借地権部分に相当する経済的価値の移転の対価として権利金等の授受が広く行われている。そして、かかる権利金等の授受の慣行が存在するにもかかわらず、法人が権利金等の授受なくして借地権を取得した際には、法人税法22条2項に基づき、「無償による資産の譲渡又は譲受け」として、当該法人に対し、権利金相当額につき認定課税を行うのが原則である。
(イ)相当の地代の支払がある場合
地主である法人が、権利金等の授受に代えて、相当の地代を収受するものとされている場合、経済的には、当該地代の資本還元額が当該土地の自用地としての価額と同等となるから、借地契約当事者間においては、
地主に当該土地の自用地としての価額がそのまま残されていて、借地権部分に相当する経済的価値は借地人に移転していないと見ることができる。したがって、このような場合、当該土地の使用に係る取引は正常な
取引条件でされたものであり、借地権部分に相当する経済的価値の移転はなかったものとして、権利金の認定課税は行われない(法人税法施行令 137 条、法人税基本通達 13- 1- 2参 照)。
一方で、借地権の設定にあたり、権利金等が授受されておらず、地代の額が相当の地代に満たない場合については、同法施行令13 7条の適用はなく、原則として、権利金の認定課税が行われることになる(法人
税基本通達13-1 -3)。
(ロ)無償返還届出書が提出されている場合
借地権の設定にあたり、権利金等が授受されておらず、地代の額が相当の地代に満たない場合であっても、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還すること(無償返還合意)が定められており、かつ、その旨を地主が借地人等との連名の書面(無償返還届出書)により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長に届け出たときは、相当の地代の額から実際に収受している地代の額を控除し
た金額に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱われ、権利金の認定課税は行われない(法人税基本通達13-1-7)。
その趣旨は、例えば同族会社とその役員等のような利害の共通する特殊な関係性を前提とすれば、将来において借地人から地主に対して借地権に係る権利主張がされることが想定されず、そのような場合にまで常に権利金の認定課税を行うとするこどは経済実態に即さないことから、無償返還合意がされ、無償返還届出書が提出されている場合には、土地所有者から借地人に対して相当の地代の額と実際に収受している地代との差額につき認定課税が行われ、権利金の認定課税は行わないことを定めたものと解される。
そして、法人税基本通達13-1-7に基づき、無償返還届出書が提出されている場合の上記のような経済実態を課税関係に反映させることには、合理性があるというべきである。
イ 地主が個人で借地人が法人である場合で、無償返還届出書が提出されているとき
地主が個人で借地人が法人である場合であっても、地主(個人)が借地人(法人)との連名で無償返還届出書を提出することは可能であるから、前記ア(ウ)のとおり、借地権の設定にあたり、権利金等が授受されておらず、地代の額が相当の地代に満たない場合であっても、無償返還合意がされ、無償返還届出書が提出されている場合、借地人である法人については、法人税基本通達13-1-7が適用され、相当の地代の額と実際に収受している地代との差額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱われ、権利金の認定課税は行われない。
(3) 検討
ア 無償返還届出書が提出されている場合の、借地権部分に相当する経済的価値の移転の有無について
前記(2)ア(ウ)の法人税基本通達13-1-7の趣旨からすれば、無償返還届出書が提出されている場合に、相当の地代の額と実際に収受している地代との差額につき認定課税が行われ、権利金の認定課税が行われないのは、相当の地代の支払がある場合(前記(2)ア(イ))と同様、借地契約当事者間においては、地主に当該土地の自用地としての価額がそのまま残されていて、借地権部分に相当する経済的価値が借地人に移転していない経済実態があるからであると解される。
そうすると、無償返還届出書の提出とは、地主が借地人との間で、将来において契約に基づき借地人から無償で土地の返還を受ける合意をしていることを届け出るものであるが、その性質は、地主が、所轄の税務署長に対し、上記の経済実態を前提にした課税上の取扱いを受けることを目的として行うものであって、課税関係において、借地権部分に相当する経済的価値が借地人に移転していないという経済実態があることを、地主自らが、所轄の税務署長に対して明らかにする趣旨の届出であるものと解するのが相当である。
イ 地主が個人で借地人が法人である場合で、無償返還届出書が提出されているときの、借地権部分に相当する経済的価値の移転の有無について
前記(2)イのとおり、地主が個人で借地人が法人である場合であっても、地主(個人)が借地人(法人)との連名で無償返還届出書を提出することは可能であるところ、無償返還届出書を提出することによって、地主(個人)は、法人税基本通達13-1-7の適用を受けることはないものの、借地入(法人)は、法人税基本通達13-1-7が適用され、借地権部分に相当する経済的価値が借地人(法人)に移転していないという経済実態を前提にした課税上の取扱いを受けることになる。そして、前記アのとおり、無償返還届出書の提出とは、借地権部分に相当する経済的価値が借地人に移転していないという経済実態があることを、地主自らが、所轄の税務署長に対して明らかにする趣旨のものであり、無債返還届出書の提出がされた場合の借地権に係る課税関係については、法人税のみならず、相続税や贈与税等に係る課税関係においても上記経済実態を前提にした取扱いがされるべきものである。
したがって、地主が個人で借地人が法人である場合で、無償返還届出書が提出されているときには、地主(個人)の譲渡所得に係る課税関係においても、地主が自ら届け出た上記の経済実態(借地権部分に相当する経済的価値が借地人に移転していない結果として、当該土地賃貸借契約の相手方である地主(個人)の下に借地権部分に相当する経済的価値が残っているという経済実態)を前提にした取扱いがされるべきものと解するのが相当である。」
ダウンロード資料